その女アレックス [書評]

文春がいつになく力を入れている翻訳ミステリーが「その女アレックス」。
”その”とあるように、ある一人の女性が主人公なのだが、注目すべきは、物語の展開の意外性。音楽に例えるなら、懐かしの70代プログレのように<転調>が激しいのだ。
全体は3部に分かれた構成となっており、
第一部は、ある男に監禁され、拷問のような状態で、殺されようとしているアレックスを描く。
捕えた男の正体は? アレックスは無事逃げ出されるのか?
糞便垂れ流しの描写があったりして、これまでのミステリーならそんな描写は描かないのだが、女性が主人公であれ、描いてしまう、ちょっと変わった作者の感覚が面白い。
第二部は死の間際で逃げ出したアレックスの意外な行動になる。アレックスってそういう女なの? と、意外性に違和感を覚えつつ、引き込まれて読み進めてしまう。
そして第三部は・・・・・
ネタバレになってしまうので、これ以上は書けないのだが、第三部になって物語の全貌が明らかになる。
三部はこれまでとも大きく異なった展開となり、読み進めてゆくうちに、グロテスクな(残酷描写ではなく精神的に)、おぞましさがじんわりと浮かび上がってきて、ここでも意表を突かれる。リアリティという部分ではどうかとも思いつつ、、、、。
もろ手を挙げての大絶賛とはいささかおおげさな気もするが、物語の意外性に引き込まれ、最後まで一気に読んでしまう作品であるのは間違いない。グロいが。
さよなら!僕らのソニー [書評]
何やら感傷的なタイトルですが、そう付けざるを得ない作者の思い入れがたっぷり注入された著書。
別に悪口を言いたいわけじゃない。じゃないけれど、言わずにおれない胸の内、察してくだせえ、皆の衆、、、とな。
<ソニー神話>なる言葉が意味を持っていた、80年代。ウォークマンはまさに革新的だった。音楽を外に持ち出せるなんて、誰が想像しただろう? 家で聴いて、外でも聴いて、場所が変われば同じ音楽でもまったく別に思えた。
そしてプレイステーション、パソコンのVAIOへと、ソニーが生み出す機器は、単なる物を超えて、わくわくした楽しさを与えてくれたものだ。
それに比べて今のソニーの低迷はいかんともし難く、特にハワード・ストリンガー氏が全権を握るようになってからは、ソニーの存在理念であった、「誰も考えたことのないものを作る」という部分をバッサリ切り捨て、ハードではなく、ソフト(ソニー・ピクチャーズ)に力を注ぐようになった。
それはそれで時代の趨勢(すうせい)であろうし、けして悪ではないが、それをもって他部門の減少した売り上げをカバー出来るに至っていないのが実情だ。
数日前に東芝の元社員が、技術を転職先の海外企業に渡した罪で逮捕されの事件は、単にいち企業の問題ではなく、犯罪という極端なことにはならなくとも、日本から技術者がいなくなっているという、技術大国日本の凋落を象徴する事件だった。
ソニーにおいても、状況は変わりなく、これまで製品開発に携わっていた技術者が、ソニーを辞めざるを得ない立場に追いやられた苦い現実が物語っている。
会社が、新製品の開発に不可欠な技術者を辞めさせたということは、新製品はいらないと宣言したに等しい。製薬会社を例に取れば、うちはジェネリックしか作らないから、開発しなくていい、と、言っているのと同じことなのだ。
実はボクも、約1年前にソニー製のブルーレイレコーダーを購入し、初日から録画に失敗し、修理に出した経験がある。結果は初期不良。技術のソニーに憧れがあった世代としては、どういうこと??? と、その思いが一気に崩壊したのだった。
テレビ事業の分社化、VAIOの売却、コンピューター事業からの撤退、保有する土地の売却、と、たまに新聞紙面を飾ったかと思えば、負の話題ばかり。これでは著者でなくとも、ソニーよ、どこへ行く? と、問い詰めたくもなる。
社内の権力闘争やハワード・ストリンガーCEO&会長の問題等は、ぜひ本文をご覧いただきたい。
世界規模の大会社となったが故の苦悩もありありと書き記しつつ、それでもやっぱり、「さよなら!僕らのソニー」と言うに至った胸の内が、哀しい。
別に悪口を言いたいわけじゃない。じゃないけれど、言わずにおれない胸の内、察してくだせえ、皆の衆、、、とな。
<ソニー神話>なる言葉が意味を持っていた、80年代。ウォークマンはまさに革新的だった。音楽を外に持ち出せるなんて、誰が想像しただろう? 家で聴いて、外でも聴いて、場所が変われば同じ音楽でもまったく別に思えた。
そしてプレイステーション、パソコンのVAIOへと、ソニーが生み出す機器は、単なる物を超えて、わくわくした楽しさを与えてくれたものだ。
それに比べて今のソニーの低迷はいかんともし難く、特にハワード・ストリンガー氏が全権を握るようになってからは、ソニーの存在理念であった、「誰も考えたことのないものを作る」という部分をバッサリ切り捨て、ハードではなく、ソフト(ソニー・ピクチャーズ)に力を注ぐようになった。
それはそれで時代の趨勢(すうせい)であろうし、けして悪ではないが、それをもって他部門の減少した売り上げをカバー出来るに至っていないのが実情だ。
数日前に東芝の元社員が、技術を転職先の海外企業に渡した罪で逮捕されの事件は、単にいち企業の問題ではなく、犯罪という極端なことにはならなくとも、日本から技術者がいなくなっているという、技術大国日本の凋落を象徴する事件だった。
ソニーにおいても、状況は変わりなく、これまで製品開発に携わっていた技術者が、ソニーを辞めざるを得ない立場に追いやられた苦い現実が物語っている。
会社が、新製品の開発に不可欠な技術者を辞めさせたということは、新製品はいらないと宣言したに等しい。製薬会社を例に取れば、うちはジェネリックしか作らないから、開発しなくていい、と、言っているのと同じことなのだ。
実はボクも、約1年前にソニー製のブルーレイレコーダーを購入し、初日から録画に失敗し、修理に出した経験がある。結果は初期不良。技術のソニーに憧れがあった世代としては、どういうこと??? と、その思いが一気に崩壊したのだった。
テレビ事業の分社化、VAIOの売却、コンピューター事業からの撤退、保有する土地の売却、と、たまに新聞紙面を飾ったかと思えば、負の話題ばかり。これでは著者でなくとも、ソニーよ、どこへ行く? と、問い詰めたくもなる。
社内の権力闘争やハワード・ストリンガーCEO&会長の問題等は、ぜひ本文をご覧いただきたい。
世界規模の大会社となったが故の苦悩もありありと書き記しつつ、それでもやっぱり、「さよなら!僕らのソニー」と言うに至った胸の内が、哀しい。
『俺はまだ本気出してないだけ』 [書評]

なんか、わかるよなあ~というタイトル。
思えば、自分の希望通りに、豊かな人生を送っている人って、どれくらいいるのだろう?
子どもの頃は、宇宙飛行士になりたいだとか、電車の運転手、野球選手、ケーキ屋さん、とか、明確にあったりしたのだけれども、中学生になると、なんとなくそれがぼやけてきて、曖昧になってしまう。
このコミックの主人公は、40歳で突然会社を辞め、突如、漫画家になると宣言。
しかし、漫画家になることが子どもの頃の夢だったかというと、どうやらそうでもないらしく、なんで漫画家なの? と、家族に問われて、自問したりしてしまう。
その上、肝心の漫画が下手!
当然、ボツになる。
口の悪い父親、娘との三人暮らし。
ハンバーガーショップでアルバイトをしている。
そんな漫画は、<いい年こいて自分探し>かよ、と、呆れもするが、この主人公のように、突然の辞表提出、まわりの迷惑かえりみず、漫画家ーっ!!!
なんて、誰でも一度や二度は考えたことがあるはずだ。
それが若いうちはいいが、結婚して、子どもが生まれ、、、と、どんどん逃げられなくなってしまうんだよね。
かといって、じゃあ、結婚もせず、独身だからって気楽かというと、そんなこともないのであって、結局、どっちに転んでも身動き取れないぞ、と。
大人になっちゃったけど、なんか違和感があるんだよなあ~という思いを抱く、すべての中年に捧げる挽歌なこの作品に、大声では言えないけれど、共感を覚えてしまう、ワタシも中年。
※ 堤真一主演の同名映画もいい感じです。
『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』 [書評]
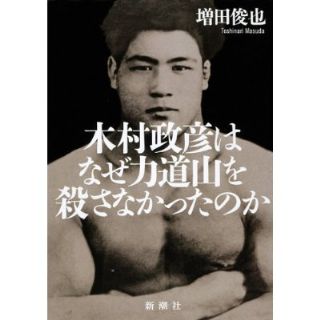
ぶ、ぶ厚過ぎるぜ!!
ページ数700、それも上下二段。価格も¥2,600とは、まさにBIGサイズ。
しかし、読み始めると止まらない。ちなみにワタクシの場合、二週間で読み終わってしまった。もっと読みたかったぜ!! と、思わず心の中で叫ぶこと間違いなしの超面白本なのだ。
歴史的な力道山と木村政彦の試合は、結果だけなら誰でもが知っているように、力道山のK.O勝ち。
プロレス・ファンを自認するワタクシも、取り立てて騒ぐことなく、その結果をごく当たり前に受け入れていた。
現在、この試合の様子は不完全な状態ながら(編集されている)、YouTobeで観ることが可能で、最初はごく普通のプロレスの試合が、途中から荒れ、不穏な空気を漂わせつつ、力道山の猛スパートで決着するのだが、猛スパートがけっこうえげつなく、プロレスの範疇を逸脱しているように見えなくもない。
本書はその試合から遡り、天才と詠われた木村政彦の柔道時代のエピソードを描きつつ、封印された<裏日本柔道史>をひも解く。近代的な講道館柔道と、高専柔道(寝技に特化した柔道)の確執から、抹殺された高専柔道の流れの中に木村政彦もいた。
最強の称号を得ながら、高専柔道というアウトサイダーゆえ、王道を歩くことを拒否され、妻の病気を治す薬を買う金を得るためにプロ柔道をやり、やがてプロレス界へ身を投じることになる。
プロレスは台本のあるショーである。とは、おおっぴらには言いたくはないものの、その事実は、今や誰でもが知る事実。しかし、力道山と木村政彦の試合が行われた1954年当時はどうだろう? 一般の人は100%真剣勝負だと思っていたはずだし、国民的英雄の力道山が、実は朝鮮出身者だとは誰も知らなかった。
あの試合も、どちらが勝つかの筋書きはあった。それにもかかわらず、力道山はおきて破りの攻撃を木村に浴びせ、K.Oしてしまう。いくら天才で最強の木村とて、安心し切っているところに、ガツン! と、本気の一撃を受けたらひとたまりもあるまい。マットに崩れ落ちてゆくしかないのだ。
そうとはいえ、木村自身にも慢心していたと指摘されてもしかたない部分が多過ぎた。
前日まで深酒をしていたとか、明らかに練習不足だったというのでは、同情の余地はない。力道山との間にきな臭い匂いは漂い過ぎるくらい漂っていた。なのに、万が一を想定しなかったのは、いったいどうしたことか?
この本を読むと、最強とかそうじゃないとかの前に、残念ながら、木村は負けるべくして負けたのだ。
帰るべき祖国を失った力道山は、どんな手を使ってでも、ここ日本でのし上がってゆくしかなかった。その違い。
大山倍達が出てきたり、ヤクザとのかかわりや、木村のいたずら好きな一面、そして、ブラジルに渡り、グレイシー一族の長であるエリオとの死闘など、読んでいて引き込まれるエピソード満載のこの本、¥2.600は安いでしょう!!!
「甲賀忍法帖」(山田風太郎) [書評]

いつも何かしらの本は読んでいるのだが、おっくうでぜんぜん書き記していなかった。
別に誰かが困るわけでもないから、いいっていえば、いいんだけれど。
山田風太郎といえば、親戚の家の古びたトイレに、文庫本が置いてあったような記憶がある。
まだボクが子どもの頃の話なので、もうかなり昔のことだけれど、今はなき母方のおじいちゃんが割と本好きで、特に時代ものが多かった。あと、小説×××とかの四六版サイズのエロ話も載っているやつ。
トイレ(昔ながらに便所と呼んだ方がしっくりくるが)にそんな本が置いてあると、子どもながら、ドキドキして読んだ(見た?)ものだ。
山田風太郎は、ご存じの如く、戦後日本を代表する大作家の一人であり、推理小説はもとより、歴史小説、特に忍者を主人公にした伝奇小説、エンターテインメント&エロな娯楽作品を数多く発表した鬼才。
「甲賀忍法帖」は1958年に書かれた、その後に続く忍法もののはしり。
時代は慶長十九年。七十三歳になる家康が、跡取りを竹千代にするか、国千代にするかに悩んだ末、甲賀と伊賀の精鋭忍者各十人を代理として戦わせ、勝った方を跡取りとするというもの。
実在の人物を登場させながら、忍者たちは架空の存在で、それも奇想天外な忍術を駆使して、相手を抹殺しようとする。
とにかく、それぞれの忍者固有の忍術が突拍子もなく、唾が超強力な接着剤のようになって飛んだり、ひとにらみすると、相手を自在に操れたり、手足のない芋虫のようだったり、切られても切られても再生する忍者だったりと、こちらの想像を大きく上回り、あっ! と、驚かせてくれる。
計二十人の忍者の中には当然女の忍者もいて、それがまたエロさ満開なのだ。肉体的に興奮すると、息に毒が混じり、相手を殺してしまうとか、まったくよくもまあ、こんなに次から次へと考えつくものだと、半ば呆れてしまう。
それでもエンターテインメントとしてとても良く出来ているので、どんどんと読み進んでしまうのだ。
甲賀、伊賀の忍者たちが次々と死んでゆく中、詩情溢れるラストなど、やはり感動してしまう。
いやはや、まったくもって、侮りがたしの一冊だ。
『屍者の帝国』 [書評]
この文章は一人の女性のみが読むことを想定して書かれたものであり、
伝達の便宜上、ここに記載する。
【登場人物について】
この物語の中の登場人物及び物語の中で語られる人物は、実在した人物であったり、有名な小説の中の人物であったりと、実在と架空が同一線上に存在している。
例を挙げると、プロローグに登場するヴァン・ヘルシング教授は、ブラム・ストーカー著『吸血鬼ドラキュラ』に登場する架空の人物であるにも関わらず、大学の講義に招かれ、小説上で与えられた精神医学を専門としつつ、バンパイアに詳しいという設定はそのまま引き継いだ形でここに登場する。
また、フローレンス・ナイチンゲールは実在の人物であり、統計学に秀でている事実をもとに、ここでは国際赤十字団統計処理部門の長の椅子を占めた統計学者と紹介され、ほぼ現実との一致が見られる一方で、俗称、フランケンシュタイン三原則を提唱したとされるが、これは架空の話で、三原則のオリジナルは、アイザック・アシモフ著『わたしはロボット』で紹介されているロボット三原則だと思われる。
このような一例を出すまでもなく、『屍者の帝国』の登場人物たちの多くは、オリジナルからの引用&部分的改ざんから成っている。
【物語の構造について】
先に挙げたように、虚実混ぜ合わさった人物が、本来、存在すべき時代を無視して登場すると、まず読者は混乱をきたす。これを回避するには、十分な知識を備えているか、もしくはまったく知識を持たないかのどちらかである。
時間軸を縦方向に延びる直線と仮定するならば、『屍者の帝国』は、それを、まるで上から押しつぶして、横方向に平べったくしたものともでも言えば良いか? すると本来異なった時間軸に存在するはずの者が、横方向、すなわち、同じ時代に存在することになる。こうして物語は、多種多様な登場人物が、一緒に登場することとなった。
【第一部】
屍者の暴走事件が相次ぐ中、それを陰で操っていると思わしきザ・ワンの存在が浮かび上がる。ザ・ワンとは、フランケンシュタイン博士によって生み出された人造人間の名称。<最初の屍者>という意味でそう呼ばれているようだ。
一方、屍者の王国を建設しようとする人物として登場する(後に違うことが判明する)アリョーシャは、ドストエフスキー著『カラマーゾフの兄弟』の三男である。彼以外にこの大長編からは、長男ドミトリィ、ゾシマ宗長、アリョーシャを崇拝するまだ若いクラソートキンが登場し、『カラマーゾフの兄弟』を経て、未完に終わった続編をなぞる。書かれなかったそれは、聖職者であるアリョーシャがゾシマ宗長の死によって宗教に疑問を持ち、聖職者の衣を脱ぎ棄て、民衆の立場からロシア皇帝を暗殺すべく行動を起こすというもの。そして彼を崇拝するクラソートキン少年がその右腕的な役割を担う。『カラマーゾフの兄弟』での関係はそのまま引用されているが、目的は皇帝暗殺を視野に入れながらも、その手段の一環としての屍者の王国の建設に趣が置かれている。現在の社会システムを覆すという革命的目的意識は当然そのまま受け継がれていることは言うまでもない。
しかし、アリョーシャは、屍人の王国を完成させる前に自ら屍者となる。生きたまま屍者化する技術をワトソンたちに知らしめるために。
ここでは、「屍者=死んだ者を生き返らせた存在」だという定義が崩され、生者に対し<死>を媒介させないで屍者とすることが出来るのが示される。いわゆる生きながら屍者となるのである。アリョーシャの兄、ドミトリーがそれだったし、アレクセイが実践して見せた。
ちなみにドミトリーが願ったのが、死者の完全復活。それは多分に聖書の中の<最後の審判>において、すべての死者が蘇るとされる光景を彷彿とさせる。、
また、アリョーシャが潜んでいる帝国にワトソン一向が向かう場面は、まるで『地獄の黙示録』だ。そうなるとさながらアリョーシャはカンボジアの密林奥深くに自らの王国を築き君臨するカーク大佐(マーロン・ブランド!)となり、ここでも別の物語と設定の引用が大胆に行われている。
【第二部】
第一部が『カラマーゾフの兄弟』の多大なる影響下にあるのに対し、第二部は舞台を東京に移し、新たな展開を見せる。しかし、第一部に比べると、屍者の軍隊とも呼ぶ戦闘集団と化した彼らとの戦闘シーンが2度もあるものの、それ自体よりは、いささかややこしいワトソンとピンカートン社の謎の美女ハダリーの禅問答のようなやり取りが前半の肝となる。これまた『カラマーゾフの兄弟』に置き換えるとすると、ゾシマ宗長とアリョーシャが交わしたやり取りと言えなくもない。
大里大学(屍者技術を開発していた施設を母体とする)で遭遇した、生者の能力を超えた屍者は、フランケンシュタイン三原則を逸脱した新たな脅威となった。また、彼らを操るフランケンシュタイン博士によって作られた最初の屍者 “ザ・ワン” からのメッセージにより、初めて彼が確固たる存在としてワトソンたちの前に立ちはだかることとなった。と、同時に、屍者の秘密が書かれていると言われている「ヴィクターの手記」とそのコピーであるパンチカードの存在が明白となる。
屍者との戦闘の後、コレラにかかって病床に伏したワトソンとハダリーとの会話は、奇妙なこの物語の<核>の一端に触れる重要な部分だ。すなわち、死者と生きている者を区別する要因は<魂>の存在の有無にあるということ。<魂>を巡るワトソンとハダリーの会話の噛み合わなさ加減が笑える。また、ハダリーが異常に高度の計算能力を有する<異能者>であることもここで判明する。
第二章の後半は、浜離宮での戦闘と、<異能者>としてのハダリーが、ザ・ワンと同じく、屍者を暴走させる力があることが示される。<魂>を感じ取ることが出来ないこの美女は、ザ・ワンによってリリスと呼ばれて、特別な位置づけを与えられる。「リリス=神によってアダムと同時に作られた最初の女性」として。このことは第三章に引き継がれ、大きな意味を持つこととなる。余談だが、『新世紀エヴァンゲリヲン』にも同等のモチーフを用いた設定あり。そちらではリリスはシンジ君の母親だった。
<異能者>としてのハダリーをより強く印象付けるエピソードとして、バトラーとの関係が語られるのも興味深い。
【第三部】
いよいよザ・ワンのいる教会に乗り込むワトソンたち。そこで待ち構えていたザ・ワンとハダリーの屍者を巡る主導権争い(どちらが操るか)が繰り広げられる中、チャールズ・ダーウィンが登場。ザ・ワンを捕え、一行は巨大戦艦ノーチラス号に乗り込む。そこで語られるザ・ワンのモノローグは、第二部でのワトソンとハダリーの会話の続編であるかのような内容となっている。自らの生い立ちと、<魂>について。
<魂>は人間だけに備わっている特殊なものであり、人間以外の動物が魂を持たないのは、魂の言葉を理解出来ないからに他ならない。だから動物は屍者にはなれない。では、その<魂>とはなんなのか? ザ・ワンは数々の実験の結果、<菌株>こそそれだという思いに至る。人はこの<菌株>に操られているに過ぎないと。そして死者だけでなく、生きている者をも屍者化する<菌株>を<不死化した菌株>と定義するならば、それらはやがてすべての人々を覆い尽くし、最後には人類を滅亡へ導くに違いない。今はまだそこまで至っていないが、数十年後、気がついた時には現実になっているはずだ。
ザ・ワンは生者の屍者化を推進する解析機関によってそれがもたらされるのを良しとしない。そこでワトソン一向とともに、ロンドン塔にあるセント・ジョン礼拝堂へ向かうこととなる。しかし、そこにはザ・ワンの好敵手とでも呼ぶべきヴァン・ヘルシングが待ち構えていた。彼は屍者の存在を認める側に立ち、ザ・ワンと敵対するが、ドミトリーのようにすべての死者の復活を望んでいるわけではない。あくまで自分たちがコントロール可能であり、屍者化の主導権を握れる立場を維持することが重要であった。一方、ザ・ワンにとっては、実は屍者や死者、さらにはかつて生あったすべての命が復活する秘儀を行うことにより、かつて作られた自分の花嫁=イヴの復活のみが目的だった。結局、イヴは復活し、ザ・ワンとともにその場から姿を消す。すべての命の復活は、<魂=菌株=言葉>の結晶石の力で制止される。
かなり込み入った話なので、素直に理解しがたい箇所多し。誰がどういう立場で、何を目的として、どう行動したのか? 読みながらメモでも取らないと辛いかも。
【エピローグ】
ワトソンがフライデーの身体の中に隠していた結晶石を取り出し、自らの体内に埋め込む。それによって敵対する2つの組織から狙われる存在となり、皮肉にもそのことが彼自身を生き永らえさせる唯一の方法となるのだった。ワトソンは天才によって生み出されたもう一人のザ・ワンとでも呼ぶべきハダリー(=リリス アダムとともに最初に神によって作り出された女性)の特殊な力を借り、それを成し遂げる。
エピローグの最後は、記録する屍者として、ワトソンのそばにいながら、今度の事件をずっと書き記してきたフライデーのモノローグで幕を閉じる。それは、記録者としての任務を解任され、初めて自我を持ったかのような記述だ。
生きながら屍者となったワトソンは、多分、自分が屍者であることも理解出来ず、普通の生活を送っている。それを眺めるフライデーの眼差しはどこか寂しそう。それでも彼が ”生きて” くれているだけで喜びが滲み出てくる(まるでフライデーが人間になったかのような錯覚を持つ。もしかしたら屍者であっても、生きていた時と同じような感情を失っていないのかも知れないが)。
彼は探偵とつるんでいるワトソンをいつか自分の手元に取り戻したいと願う。その探偵とは、当然、シャーロック・ホームズその人であり、となると、フライデーはモリアティ教授ということになる。それを裏付けるように、この物語は1881年で終わるが、ワトソンがシャーロック・ホームズと出会うのもまた1881年なのである。なので、この物語の続きはそちらの本を参照に・・・なのかな?
結局、この物語は<魂>を巡る物語であり、それはすなわち<言葉>を巡る物語と言える。聖書の最初の一説にはこうある。
初めに言葉ありき
言葉は神とともにありき
神は言葉であった
伝達の便宜上、ここに記載する。
【登場人物について】
この物語の中の登場人物及び物語の中で語られる人物は、実在した人物であったり、有名な小説の中の人物であったりと、実在と架空が同一線上に存在している。
例を挙げると、プロローグに登場するヴァン・ヘルシング教授は、ブラム・ストーカー著『吸血鬼ドラキュラ』に登場する架空の人物であるにも関わらず、大学の講義に招かれ、小説上で与えられた精神医学を専門としつつ、バンパイアに詳しいという設定はそのまま引き継いだ形でここに登場する。
また、フローレンス・ナイチンゲールは実在の人物であり、統計学に秀でている事実をもとに、ここでは国際赤十字団統計処理部門の長の椅子を占めた統計学者と紹介され、ほぼ現実との一致が見られる一方で、俗称、フランケンシュタイン三原則を提唱したとされるが、これは架空の話で、三原則のオリジナルは、アイザック・アシモフ著『わたしはロボット』で紹介されているロボット三原則だと思われる。
このような一例を出すまでもなく、『屍者の帝国』の登場人物たちの多くは、オリジナルからの引用&部分的改ざんから成っている。
【物語の構造について】
先に挙げたように、虚実混ぜ合わさった人物が、本来、存在すべき時代を無視して登場すると、まず読者は混乱をきたす。これを回避するには、十分な知識を備えているか、もしくはまったく知識を持たないかのどちらかである。
時間軸を縦方向に延びる直線と仮定するならば、『屍者の帝国』は、それを、まるで上から押しつぶして、横方向に平べったくしたものともでも言えば良いか? すると本来異なった時間軸に存在するはずの者が、横方向、すなわち、同じ時代に存在することになる。こうして物語は、多種多様な登場人物が、一緒に登場することとなった。
【第一部】
屍者の暴走事件が相次ぐ中、それを陰で操っていると思わしきザ・ワンの存在が浮かび上がる。ザ・ワンとは、フランケンシュタイン博士によって生み出された人造人間の名称。<最初の屍者>という意味でそう呼ばれているようだ。
一方、屍者の王国を建設しようとする人物として登場する(後に違うことが判明する)アリョーシャは、ドストエフスキー著『カラマーゾフの兄弟』の三男である。彼以外にこの大長編からは、長男ドミトリィ、ゾシマ宗長、アリョーシャを崇拝するまだ若いクラソートキンが登場し、『カラマーゾフの兄弟』を経て、未完に終わった続編をなぞる。書かれなかったそれは、聖職者であるアリョーシャがゾシマ宗長の死によって宗教に疑問を持ち、聖職者の衣を脱ぎ棄て、民衆の立場からロシア皇帝を暗殺すべく行動を起こすというもの。そして彼を崇拝するクラソートキン少年がその右腕的な役割を担う。『カラマーゾフの兄弟』での関係はそのまま引用されているが、目的は皇帝暗殺を視野に入れながらも、その手段の一環としての屍者の王国の建設に趣が置かれている。現在の社会システムを覆すという革命的目的意識は当然そのまま受け継がれていることは言うまでもない。
しかし、アリョーシャは、屍人の王国を完成させる前に自ら屍者となる。生きたまま屍者化する技術をワトソンたちに知らしめるために。
ここでは、「屍者=死んだ者を生き返らせた存在」だという定義が崩され、生者に対し<死>を媒介させないで屍者とすることが出来るのが示される。いわゆる生きながら屍者となるのである。アリョーシャの兄、ドミトリーがそれだったし、アレクセイが実践して見せた。
ちなみにドミトリーが願ったのが、死者の完全復活。それは多分に聖書の中の<最後の審判>において、すべての死者が蘇るとされる光景を彷彿とさせる。、
また、アリョーシャが潜んでいる帝国にワトソン一向が向かう場面は、まるで『地獄の黙示録』だ。そうなるとさながらアリョーシャはカンボジアの密林奥深くに自らの王国を築き君臨するカーク大佐(マーロン・ブランド!)となり、ここでも別の物語と設定の引用が大胆に行われている。
【第二部】
第一部が『カラマーゾフの兄弟』の多大なる影響下にあるのに対し、第二部は舞台を東京に移し、新たな展開を見せる。しかし、第一部に比べると、屍者の軍隊とも呼ぶ戦闘集団と化した彼らとの戦闘シーンが2度もあるものの、それ自体よりは、いささかややこしいワトソンとピンカートン社の謎の美女ハダリーの禅問答のようなやり取りが前半の肝となる。これまた『カラマーゾフの兄弟』に置き換えるとすると、ゾシマ宗長とアリョーシャが交わしたやり取りと言えなくもない。
大里大学(屍者技術を開発していた施設を母体とする)で遭遇した、生者の能力を超えた屍者は、フランケンシュタイン三原則を逸脱した新たな脅威となった。また、彼らを操るフランケンシュタイン博士によって作られた最初の屍者 “ザ・ワン” からのメッセージにより、初めて彼が確固たる存在としてワトソンたちの前に立ちはだかることとなった。と、同時に、屍者の秘密が書かれていると言われている「ヴィクターの手記」とそのコピーであるパンチカードの存在が明白となる。
屍者との戦闘の後、コレラにかかって病床に伏したワトソンとハダリーとの会話は、奇妙なこの物語の<核>の一端に触れる重要な部分だ。すなわち、死者と生きている者を区別する要因は<魂>の存在の有無にあるということ。<魂>を巡るワトソンとハダリーの会話の噛み合わなさ加減が笑える。また、ハダリーが異常に高度の計算能力を有する<異能者>であることもここで判明する。
第二章の後半は、浜離宮での戦闘と、<異能者>としてのハダリーが、ザ・ワンと同じく、屍者を暴走させる力があることが示される。<魂>を感じ取ることが出来ないこの美女は、ザ・ワンによってリリスと呼ばれて、特別な位置づけを与えられる。「リリス=神によってアダムと同時に作られた最初の女性」として。このことは第三章に引き継がれ、大きな意味を持つこととなる。余談だが、『新世紀エヴァンゲリヲン』にも同等のモチーフを用いた設定あり。そちらではリリスはシンジ君の母親だった。
<異能者>としてのハダリーをより強く印象付けるエピソードとして、バトラーとの関係が語られるのも興味深い。
【第三部】
いよいよザ・ワンのいる教会に乗り込むワトソンたち。そこで待ち構えていたザ・ワンとハダリーの屍者を巡る主導権争い(どちらが操るか)が繰り広げられる中、チャールズ・ダーウィンが登場。ザ・ワンを捕え、一行は巨大戦艦ノーチラス号に乗り込む。そこで語られるザ・ワンのモノローグは、第二部でのワトソンとハダリーの会話の続編であるかのような内容となっている。自らの生い立ちと、<魂>について。
<魂>は人間だけに備わっている特殊なものであり、人間以外の動物が魂を持たないのは、魂の言葉を理解出来ないからに他ならない。だから動物は屍者にはなれない。では、その<魂>とはなんなのか? ザ・ワンは数々の実験の結果、<菌株>こそそれだという思いに至る。人はこの<菌株>に操られているに過ぎないと。そして死者だけでなく、生きている者をも屍者化する<菌株>を<不死化した菌株>と定義するならば、それらはやがてすべての人々を覆い尽くし、最後には人類を滅亡へ導くに違いない。今はまだそこまで至っていないが、数十年後、気がついた時には現実になっているはずだ。
ザ・ワンは生者の屍者化を推進する解析機関によってそれがもたらされるのを良しとしない。そこでワトソン一向とともに、ロンドン塔にあるセント・ジョン礼拝堂へ向かうこととなる。しかし、そこにはザ・ワンの好敵手とでも呼ぶべきヴァン・ヘルシングが待ち構えていた。彼は屍者の存在を認める側に立ち、ザ・ワンと敵対するが、ドミトリーのようにすべての死者の復活を望んでいるわけではない。あくまで自分たちがコントロール可能であり、屍者化の主導権を握れる立場を維持することが重要であった。一方、ザ・ワンにとっては、実は屍者や死者、さらにはかつて生あったすべての命が復活する秘儀を行うことにより、かつて作られた自分の花嫁=イヴの復活のみが目的だった。結局、イヴは復活し、ザ・ワンとともにその場から姿を消す。すべての命の復活は、<魂=菌株=言葉>の結晶石の力で制止される。
かなり込み入った話なので、素直に理解しがたい箇所多し。誰がどういう立場で、何を目的として、どう行動したのか? 読みながらメモでも取らないと辛いかも。
【エピローグ】
ワトソンがフライデーの身体の中に隠していた結晶石を取り出し、自らの体内に埋め込む。それによって敵対する2つの組織から狙われる存在となり、皮肉にもそのことが彼自身を生き永らえさせる唯一の方法となるのだった。ワトソンは天才によって生み出されたもう一人のザ・ワンとでも呼ぶべきハダリー(=リリス アダムとともに最初に神によって作り出された女性)の特殊な力を借り、それを成し遂げる。
エピローグの最後は、記録する屍者として、ワトソンのそばにいながら、今度の事件をずっと書き記してきたフライデーのモノローグで幕を閉じる。それは、記録者としての任務を解任され、初めて自我を持ったかのような記述だ。
生きながら屍者となったワトソンは、多分、自分が屍者であることも理解出来ず、普通の生活を送っている。それを眺めるフライデーの眼差しはどこか寂しそう。それでも彼が ”生きて” くれているだけで喜びが滲み出てくる(まるでフライデーが人間になったかのような錯覚を持つ。もしかしたら屍者であっても、生きていた時と同じような感情を失っていないのかも知れないが)。
彼は探偵とつるんでいるワトソンをいつか自分の手元に取り戻したいと願う。その探偵とは、当然、シャーロック・ホームズその人であり、となると、フライデーはモリアティ教授ということになる。それを裏付けるように、この物語は1881年で終わるが、ワトソンがシャーロック・ホームズと出会うのもまた1881年なのである。なので、この物語の続きはそちらの本を参照に・・・なのかな?
結局、この物語は<魂>を巡る物語であり、それはすなわち<言葉>を巡る物語と言える。聖書の最初の一説にはこうある。
初めに言葉ありき
言葉は神とともにありき
神は言葉であった
『真夜中の電話』(ロバート・コーミア) [書評]
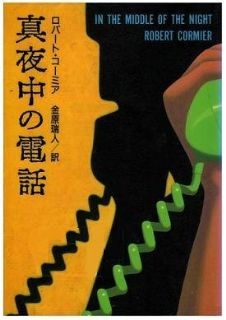
『真夜中の電話(In The Middle Of The Night)/ロバート・コーミア』(扶桑社ミステリー)
一部翻訳ミステリー・ファンの間ではカルト的人気を誇るロバート・コーミア。
代表作は映画にもなった『チョコレートウォー』(1973)で、以降、地味ながらもここ日本でも10冊近い翻訳が出版されている。
コーミアを象徴する見出しを付けるなら、<青春ミステリーの巨匠!>かな?
この『真夜中の電話』は1995年の作品。
デニー少年の父、ジョン・ポールは、学生の時に劇場でアルバイトをしていた。その劇場はかなり古く、建物の強度を不安視されていた。ある日、子どもたちが集まるイベントの日の夜、ジョン・ポールは、2階からするきしみ音の原因を見つけに火を手に暗闇を覗いていたのだが、誤って手にした火を燃え移らせてしまう。それと同時に、2階の観客席が落ち、下にいた人たちを直撃。結果、22人もの人たちが犠牲になる大惨事となってしまう。
それ以来、ジョン・ポールは事件の直接の原因を作ったわけではなかったにもかかわらず、街から街へ、逃げるようにしてひっそりと暮らしていた。
時は流れ、ジョン・ポールの息子デニーのもとに一本の電話がかかってくる。ルルと名乗った女性は過去の大惨事と関係があるようなのだが・・・。
物語設定は上手い。特異なシチュエーション提示はコーミア独特なもので、それだけでこの作家が平凡なミステリー作家ではないことがうかがわれる。しかし、単にストーリーだけを見れば、ツカミは抜群なのに、その後が今一つなのは惜しい。そこがコーミアを人気作家の地位に持ち上げるのを妨げているような「気がする。
だからミステリーとして読むと、ルルという人物の種明かしも別にどうということはない。正直、え? これなの? って感じなのだ。嫌な言い方をすると、肩すかし。
では、どこが面白いのか?
それは、まず、冒頭にも記した通り、「青春ミステリー」として、10代の少年少女の心情とか、若さに翻弄される登場人物とか、とにかく人物描写が上手いのだ。
それと、事件はいちおうの解決を見るが、それがそのまま主人公の心の不安を取り除きはしないという事実。普通は解決したら新しい明日に向かって歩き出せるものなのだが、コーミアの主人公に限っては、たいして状況は変わらなかったりする。事件が解決しようがしまいが、同じ陰鬱な明日が続く・・・。
これは考えてみればかなり理不尽で、なんらかのカタルシスを求める読者を煙に巻く。嫌~な気分で読み終わるのだから。読み終わった後、ハア~、、、と、ため息のひとつでもつきたくなってしまうのだから。
巻末で「特別解説座談会」と称して、3人作家や評論家の方が、コーミア読もうね! と宣伝して下さっておられるが、これまで通り、一部のファンの間でこっそりと読まれるといったこれまでの構図が実はこの作者には合っているのではないのかなと。あまりにも人気がなく、出版されないのは困りものなれど、必要以上に騒ぐ必要もないのかもねというのが、正直な感想。
『死にたい老人』(木谷恭介) [書評]

『死にたい老人/木谷恭介』(幻冬舎新書)
以前、長寿はめでたいか? と、日頃感じていた疑問をこのブログに書いたことがある。
100歳までケンコー! いつまでも若くいたい! 人生これから!
ノー天気なシュプレヒコールの嵐に、長寿はついに新興宗教と化した!!! なんて思った。
もちろん健康は尊いが、人が簡単には死ななくなって良かったねと単純に言い切ってしまうのも、はなはだ疑問なのである。
老人介護の問題は現代社会が抱えた大きな問題だし、老人の増加と少子化は、年金制度の崩壊をもたらした。
そんな現実が目も前にあるのに、そのノー天気さは無知を通り越して「悪」だ。うがった見方をすれば、健康商品を売りたいが為のメーカー側の策略でしかないのに。
それでもまだ今の老人は幸せだ。60歳にもらえるはずの年金が65歳に延長され、さらに延長をもくろむ国のバカな案が現実味を帯びているこれから老人になる我々にとって、60歳を過ぎ、65歳、70歳になるまで金も支給されず、社会制度も他人まかせのまま、働け、働け、とはいったいなにごとだろう?
死ぬより厳しい現実、こんなことならさっさと死んどけば良かった・・・。そんな社会がやってこようとしている。
★ ★ ★ ★
作者の木谷恭介氏は、ミステリー好きならば名前くらいはほとんどの方が知っているベテランの作家だ。
この本は83歳になった小谷氏が、体力の衰え、痴呆症への恐れ、離婚、孤独死への恐怖等々から、自らの意思で「死」を選択し、実践する経過を書き記したものである。
自殺の方法は色々あれど、氏が選択したのは「断食安楽死」だった。無理矢理に「死」に向かうのではなく、西行が行ったような断食によって死を迎えるといったものだ。そこには死にたいという感情とは別の、生きていく必然性が希薄になったとでも言うべきものであった。
断食開始前からの記述から始まり、カウントダウンをしながら、その日に食べたもの(おもにお粥)と体重が記載され、一気にではなく、徐々に身体を慣らしてゆくあたりからして、当たり前だが、すでに本気モード。それを読みながら、なかなか体重が落ちないな、とか、持病の鬱血性心不全の症状を気遣いながら薬を飲む様子等、疑似体験ではないが、こちらも慎重に読み進めてゆくことになる。
「死」に向かって断食するのに、なんで身体の心配なんてするの? と、いぶかしむ向きもあろうかと思う。それは死ねば良いというものではなく、最終的には浄化されての「死」であるべきだろうとの氏のこだわりの表れでもあろう。単に死ぬのならば、列車への飛び込みとか、練炭自殺とかの方法もあるだろうも、それは違うのだ。
さて、氏は「断食安楽死」に成功するのだろうか? でも、成功していたら新聞沙汰になっているよなあ・・・とも思うし、失敗したら失敗したで、本文中に何度も決心のほどを書き連ねているので、引っ込みがつかないんじゃないのかな・・・とも思う。人の生き死にに対して不謹慎だとも思うが、読み物として考えたら、どうしてもそうなってしまうのはいたしかたなし。でも、人はそう簡単に「理性」では死ねないもの。
とか、ドキドキというよりソワソワしながら読み進めたのだった。
とりあえず、結果はご自分でご確認下さい。
『リピート』(乾くるみ) [書評]

『リピート/乾くるみ』(文春文庫)
『イニシエーション・ラブ』でブレイク(?)した乾くるみの次作がこの『リピート』。
文庫版裏表紙の『リプレイ』 + 『そして誰もいなくなった』との説明は言い得て妙で、これだけでミステリーファンには、なるほど・・・と、うなずくこと間違いなし。つかみとしては分かりやすくて良いですね。
STORY:風間という謎の人物から任意に選ばれた9人の人物がいる。年齢も職業もバラバラだが、彼の予言が2度に渡って現実を言い当てたことで、彼の主張する<時間をさかのぼって戻ることが可能である>という話を信じざるを得なくなる。ただし、やり直せるのは10ヶ月前までらしい。
ある者は失敗した大学受験をやり直そうとし、ある者はあらかじめ記憶しておいた万馬券で金を稼ごうとする。全員が明確なビジョンを持っているわけではなかったものの、たとえ10ヶ月間だけとはいえ、やり直せるという事実に心動かされない者などいるはずもない。
リピートは成功。さてこれからそのメリットを生かして・・・という時に、一人、また一人と、リピーターたちは命を落とし始める・・・。
巻末の読み応えのある解説にもあるように、ネタもととなったであろう『リプレイ』(傑作なので未読の方はぜひ!)の多大な影響下にありながら、それだけではない独自のストーリー展開に、興味は尽きない。500ページもあるのに読みやすいため、一気に読み進めるのも嬉しい。
SFの設定でスタートし、その後は推理物となる物語は、なぜリピーターたちが殺されるのかの解答を一つの山場として、人生をやり直すことが幸せに直結しない理不尽さも感じながら、最後の結末へと雪崩れ込む。苦いエンディングもここでは必然なのかもしれない。
傑作『イニシエーション・ラブ』を読んだ後では、多少物足りなく感じてしまうことも事実だが、これはこれで平均点以上の出来ではあると思う。なので旅行のお共に持参すれば、気楽に読めることは保証します。
『楽園への疾走』(J・G・バラード) [書評]
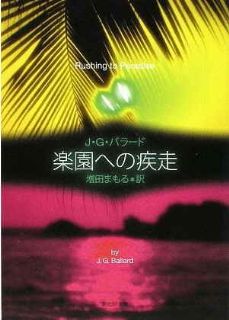
『楽園への疾走(Rushing Paradise)/J・G・バラード』(1994)
『殺す』に続いて読んでしまいました。
なんだかんだ言っても、変態好きなもので。こうなると真っ当なものでは満足出来ないんですね(笑)
だからマイナーで危ない方につい吸い寄せられてしまう。因果やねえ~。
『楽園への疾走(Rushing Paradise)』は1994年の作。偶然だが、『殺す』(1988)が<Running~>なので、イメージ的には類似点があるのかな? 暴走するようなイメージが・・・。
で、こちらは昨今の環境保護団体ピ-スボートをモデルにしたと思われる、クジラならぬアホウドリを救え! と叫ぶ女性医師バーバラが主人公。座り込みやビラ撒き、抗議のデモ等、かなりの強硬派のようだ。そんな彼女に魅せられた少年ニールは、ひょんなことから彼女と行動を共にすることとなる。
タヒチ沖の島は過去にフランスによって核実験場と化し、アホウドリも生息の危機に瀕しているのだ。そこにバーバラを筆頭に、ニール、バーバラの抗議運動に賛同した人たちが船で乗り付ける。挙句の果てに、島にいすわり、独自の生活を送り始めるのだが、いつしか環境保護運動から逸脱した異常な行動を起こし始める・・・。
環境保護運動の拠点として、その島はアホウドリともども、楽園となるはずだったのに、バーバラの不可思議な行動から不穏な雰囲気が漂い始め、やがて楽園の意味合いが根底からひっくり返ることになる。彼女にとって保護すべきなのはアホウドリなのか? それともまったく別ななにかなのか?
後半、ほとんど狂気となる彼女の "疾走" は、しかし、単なる物語の中のフィクションだとは言い切れず、ここでもやはり未来を見通すバラードの冷徹な視点で満ち満ちている。現実のグリーンピースの抗議行動を見れば、一線を越えていると日本人なら理解出来るが、どこまで行っても優越人種である白人にとっては、調査捕鯨と言う名のクジラの虐待を続ける日本の方が理解不能であるように、バーバラにとっても自分が取った行動こそが<正義>なのだった。
ならばこの作品を単なる小説と読み飛ばすことの愚を、我々は肝に銘じなければなるまい。すでにすべてを網羅する正義など、どこにもないと。正義は己の中にあり。しかし、それが正しいとは限らない・・・。
他のバラードの作品を一通り読んで、この作家がなにを考えているのか、知りたいところだ。
『殺す』(J・G・バラード) [書評]

『殺す(Running Wild)/J・G・バラード』(創元SF文庫)
あまりといえばあまりなタイトルである。
『殺す』・・・って、ズバリ過ぎね? って感じ。
原題をチェックしてみると、『Running Wild』だった。確かに日本語に置き換え難いタイトルだと思う。
でも、読み進めるうちに、この何とも物騒な邦題が、あながち的外れでもないことに気づく。
作者のJ・G・バラードは英国出身。皮肉な英国紳士らしく(?)、どこかシニカルで、不条理なテイストを物語に折り込む、特異な作家だ。映画ファンの間では、デビッド・クローネンバ^グ監督で映画化された『クラッシュ』の原作者として、知名度も高い。
なのでやっぱりというか、一筋縄ではゆかない、偏屈者だったりするので、たちが悪い。
そもそも『クラッシュ』なんて、車に乗って事故を起こし、車共々大破して死ぬのが、絶好のエクスタシーだなんて、普通の人は考えないでしょうに。挙句に突っ込むのが、憧れの映画女優だったりすれば、なおサイコーッ!!! だなんて・・・。
小説は、それをまじめに描いてます(笑)
「キモイ!!!」
今の若者たちなら、その一言で無視してしまうだろうが、中年はグロの中にエロスを垣間見ちゃったりして、ちょっとドキドキ・・・。『他人のセックスを笑うな』は山崎ナオコーラの本のタイトルだが、『他人の性癖を無視するな』と、ここのところは言ってしまいたい。
そんな彼の1988年作がこの『殺す』だ。
=ロンドン郊外の高級住宅街で、32人の大人が殺され、13人の子供が誘拐された=
なぜ彼らは殺されなければならなかったのか?
誰に殺されたのか?
誘拐された子供は無時なのか?
この3つの謎を調査することになったドクター・リチャード・グレヴィルの日記という形式で、小説は書かれている。 日記なので、必要以上に受けを狙ったり、怖がらせたりする必要はない。ただ、事件現場を歩き、そこの空気に触れ、気になったことや感じたことを、ありのままに綴っただけである。
一読するとやけにぶっきらぼうな文体にいささか戸惑いを隠せないのだが、読み進めてゆくと、淡々と書かれているがゆえに、じんわりとした不気味さを醸し出し、背筋が寒くなる。
調査の中から浮かび上がる答えは、消去法によってこれしかないと導き出されたものであり、結果に至った過程と、惨殺現場で起きたであろう "事実" を、まるで実況中継の如く、ただ語るのみである。必要以上に感情移入せず、無機的な文章は、静かであればあるほど、恐ろしさが募る。
バラードが予言者に例えられるのは、これから訪れるであろう未来社会の表向きの現象だけでなく、核となる心情すらも捕える審美眼の飛び抜けた力ゆえだろう。
それから察すると、この作品も、まさに未来を予言した書と言えるに違いない。
『ロックが熱かったころ』(中村とうよう) [書評]
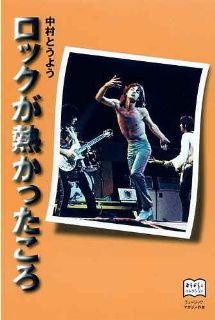
『ロックが熱かったころ/中村とうよう著』(ミュージック・マガジン)
中村とうようが亡くなった。自殺だった。
中村とうようが出版人であり、編集長であった(現在は異なる)「ミュージック・マガジン」。そしてその前身である「ニューミュージックマガジン」は、ともに、長らくボクら世代のバイブルだった。
高校生の頃はお金もないのでおもに立ち読み。ちょうど同時期に出版されていた、カラー写真満載の「音楽専科」(!)に比べて、サイズも小さく、おまけに写真も少なく記事ばっかりで、ずいぶんと地味だった。それでも彼の書く記事には一本、ピン! と筋が通っていて、妙に納得させられたものだ。
大人になって改めて購読するのだが、基本姿勢は終始一貫変わらなかった。いちおうロック・フィールドの雑誌なのに、ジャズや民族音楽にもちゃんと目配りしているところが、他の雑誌と決定的に違っていた。当時のボクはそこを飛ばし読みしていたに違いないが、今となっては、知らず知らずのうちに刷り込まれていたような気もする。
音楽にこだわりを持つ人間が減り、ヒットチャートがAKB48を代表とする、いわゆるアイドルPOPが席巻する2011年、いつの時代もこのてのジャンルが必要なのは否定しないが、暗澹たる気持ちに襲われるのも事実。もう、誰も真剣に音楽を聴こうなんて思わないんだなあ・・・と。果たしてそんな彼らが中年になった時、彼らの中で、懐古趣味以外に音楽は存在出来るんだろうか?
音楽と真剣に向き合う。「ミュージックマガジン」の編集方針の根幹はそこだった。『ロックが熱かったころ』は「(ニュー)ミュージックマガジン」誌上に掲載された中村とうようの持論を、おもにレコード評を通して紹介したもので、1970~80年代半ば頃に書かれたもので構成されている。
意味深なタイトルからもうかがえるように、ロックがロック足り得たのは、せいぜいパンク~ニューウエイブ期頃までだったように思う。今でこそ日本の歌謡曲バンドもロックと呼ばれて久しいが、いったいいつからロックが、子どもの情操教育の一貫のような、もの分かりの良さに溢れたヒーリング・ミュージックに成り下がったのか? 若者のフラストレーションの発散を根幹に持つはずのロックは、大人からは揶揄(やゆ)される、不良の音楽だったのに・・・。
そんな不良の音楽は、危険な音楽でもあった。毒をはらんだ音楽だからこそ、大人は嫌ったのである。<みんないい人>思想がロックを殺す、、、いや、現に殺してしまった。だから、『ロックが熱かったころ』なのだ。過去形なのだ。
この本の中では、スリーピー・ジョン・エステスのライブでの、日本人手拍子のまぬけさについて述べ、バカ一筋のステイタス・クォーを褒め、返す刀で、ボストンの大げさな演奏に文句をつける。
レコード評では、なんと、BONZO DOG BAND、THE FUGS、THE HOLY MODAL ROUNDERS なんてバンドを紹介。そんなの誰も知らねーよ! と、言われかねない危ういラインナップである。さらにMOTHERS を絶賛し、ランディ・ニューマンの『セイル・アウェイ』に95点を献上。逆にファウストの4枚目には厳し過ぎる20点だったりして、黒人音楽から派生したロックの持つ身体性を無視した、西欧人の頭でっかちな音楽に嫌悪感を丸出しにする徹底さがいっそ潔し!!!
このように、ハッキリものを言ってしまうので、人によっては好き嫌いがあると思う。それでも売り上げの多くを広告収入に頼っている手前、悪口の言えない商業誌の中では、やはり異彩を放っていた。
死の前には自分の音楽コレクションを知人に譲り渡していたとも聞く。
自殺の原因は定かではないし、それを詮索したところでどうなるはずもない。
ただ、音楽を聴く楽しみを教えていただいた恩人に、一言感謝を言いたかっただけだ。
ありがとうございました・・・。
『四日間の奇跡』(浅倉卓弥) [書評]

『四日間の奇跡/浅倉卓弥』(宝島社文庫)
久々に、"素直な感動" という言葉を思い浮かべてしまった。
本来はこのような無防備な感動物って嫌いなのだけど、嫌い嫌いと言いながら、でも、それなりに感動してしまう自分に、
「ああ、ボクって、本当はいい人なんだよ・・・」
と、自分を褒めてしまえる自分が好き、、、みたいな(オエ!)。
(ちなみに自分にご褒美という言葉も大嫌い!)
計算されてるんですね。感動に向かって、生真面目に物語を計算している。悪くはないんですよ、実際感動しちゃったりもするんだから。でも、どこか映画のシナリオを読んでいるような錯覚を覚えてしまうもの事実。
物語の先行きは最初から100%分かっているの。分かっていながら、いや、分かっているからこその快感ってあるじゃないですか。くるぞ、くるぞ、と身構えながら、そらきた!!! とばかりに涙腺が緩んで、いい年した大人が(いい年しているからこそ?)、ポロッと一筋の涙を流す。そして柄にもなく、新聞の読者投稿とかしちゃったり・・・。
なんか、書けば書くほど悪口言っているみたいで嫌だな。本当は、あざといけれども、けっこう良いよ~とか書くつもりだったのに。変だなあ・・・。どこで間違っちゃったんだろう??? だからヘソ曲がりとか、天邪鬼とか言われるんだよな。あ~あ。
いちおうストーリーは、
ピアニストとして羽ばたこうとした矢先、偶然遭遇した事件に巻き込まれて左手の薬指を損傷した主人公と、その事件で両親を亡くした脳に障害を持つ少女。彼女を引き取って面倒を見るうちに、彼は彼女の音楽的才能に気付き、自分の替わりにピアノを弾かせ、老人ホームへの慰問を行っている。
ある老人ホームへ慰問に訪れた時に、そこに従事する女性が、かつての高校の後輩だったことが判明する。そんな時、落雷事故が3人の運命を大きく変えることになる・・・。
ね? 感動は保証付きでしょ?
PS.500ページ近くの量を最後まで読み切ったのだから、良い小説だと思います。今さらですが。
『Jの神話』(乾くるみ) [書評]

『Jの神話/乾くるみ』(文春文庫)
『イニシエーション・ラブ』があまりにも有名になってしまい、一人歩きしている感もなくはない作者の、これはデビュー作とな。
全寮制カトリック系女子高を舞台した殺人事件という設定に萌える人多し???
まあ、これはこれで定番ではあるし、実はけっこうこういった設定って嫌いじゃないので、楽しんで読めました❤❤
とはいえ、後年の時間をパズルのように操ったタペストリー作品である『イニシエーション・ラブ』の萌芽が見られるかというと、それはそれ、これはこれ。はっきり言ってぜんぜん似てない。まあ、それはそれで構わないのだけれど。
ボクは呆気に取られながらも、こなれた文章ゆえ、サクサクと先に進めて、でも、ところどころ、マジですかあ~~と、思いながらの読書感がこそばゆかったりもして(笑)
だって、一見、女の園で起きた殺人事件ながら、途中からメディカル・ホラーの様相を呈し始め、果てはエログロ小説もどきの描写が笑える珍作、そう、まさしく珍作!!!
意図的にやってるの? と、ついチャチャを入れたくなってしまう、突っ込みどころ満載のこの作品、いちいち腹を立てないで、なすがままにその身をあずけちゃった方がいいよ~と、そう思う次第です。ハイ!
『虐殺器官』(伊藤計劃) [書評]
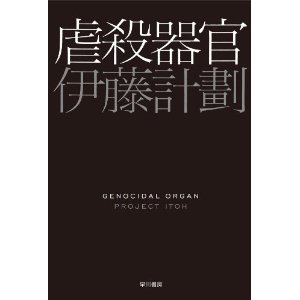
『虐殺器官/伊藤計劃』(ハヤカワ文庫)
作者の名前が読めないぞ、、、とか、
なんだ、この黒い装丁は、、、とか、
キャッチコピーの「ゼロ年世代ベストSF」第1位、、、とか、
なにやらただならぬ妖気を発しているこの本、前々から気にはなっていたのを、やっと手に取ったのであった。
単なる偶然なのか、それとも意図したのか、真黒な装丁があたかも葬儀に飾られる作者の写真のごとく、もしくは位牌のごとく感じられたりするのだが、まさにその通りで、作者はすでにこの世の人ではない。
そう考えると、遺書を保管しておく黒塗りの箱にも見えてきたりするのだから、なにをか言わん。
STORY:近未来の世界。アメリカ軍大尉シェパードは、超ハイテク特殊部隊に所属し、祖国に火の粉が降りかからないのよに、貧しい国に次々と起こる内乱や虐殺を鎮める戦いをしていた。具体的にはそれらを引き起こしていると疑われる謎の男、ジョン・ポールの暗殺だ。しかし、今一歩というところまで追い詰めながらいつも取り逃がしてしまう。
理由は分からないのだが、ジョン・ポールの現れる国は必ず内乱や大量虐殺が起こるのだ。いったい彼は何者で、なんの為にそのようなことを引き起こすのか・・・。
もうひとつ表紙に書かれたキャッチコピーが<現代における罪と罰>。近未来を舞台にしたテクノロジーに満ちた戦いの様子があちこちに描かれていながらも、どこか戦いは泥臭く、今風だ。そもそもいくらハイテク化されようとも、しょせんは命のやり取りなわけで、血も出れば、身体も損傷を受ける。その意味においては未来も過去もきっと大差ないのだろう。だからSF小説にまとわりつく空絵事はここには見事にない。SF嫌いはその点にアレルギーを持つのだが(ボクがそう)、その作品は最初から違和感なく読み進められた。
ジョン・ポールの《虐殺器官》理論は賛否両論あるかもしれないが、彼がそれを用いてなぜ血にまみれた混乱を誘発させるのかについては、一理あるかもしれない。彼の殺害指令を受けたシェパードは、ジョン・ポールの行動原理となったその考えを当然否定するのだが、100%否定出来ない思いも残ったりもする。
後半、対峙したジョン・ポールとシェパードの対話は、キャッチコピーにもある通り、ドストエフスキー『罪と罰』におけるラスコリーニコフとスヴィドリガイロフとのやり取りを彷彿とさせるし、また、『カラマーゾフの兄弟』における次兄イワンの告白にも通ずるところがある。そして最後に訪れる結末は。。。。
なるほど・・・。
最後のページをめくる手を一瞬止めたその時、妙に納得してしまう自分がいる。



