『南極1号伝説~ダッチワイフの戦後史~』 [書評]

『南極1号伝説/高月靖(文春文庫)』
文芸版で見かけて気になっていたものが、いつの間にか文庫化されていたので、迷わず購入。
ちなみに「南極1号」とは、男性なら誰でも知っている、でも、多くの女性には不明な言葉かもしれない。
ズバリ、南極観測隊の性処理用ダッチワイフの俗称。本当に使用されたのかについては、たぶん、公表されていないのではないかと思われる。それでも今や完全に伝説と化している。
そりゃあ、大手を振って持って行きました!!! みんなで使いました!!! サイコー!!!
なんて、発表出来ないし(笑)
ポルノショップにすらなかなか入った人もいないだろうし、存在そのものが半ば謎でもあるダッチワイフ。
なぜダッチ(=オランダ)なのかは横に置いておいて、ギャグにしばしば登場するビニール製の、浮き輪の人型版のようなチープなものは今では皆無。それどころか、シリコン製が主流となって、価格も一体50~60万円もする超高級品が人気。掲載されている写真を眺めると、マネキンよりももっと柔らかくて、表情や身体つきも人間そのものといった感じがするくらい精巧に作られている。名称もダッチワイフとは呼ばず、ラブドールという。
この本では、そんなラブドール製作に携わる複数の製作者へのインタビューを通して、完成までの苦労話の数々が披露されている。
素材となるシリコンがかなりの重量であるため、軽量化は避けて通れない道であり、同様に、関節をどう動かせるようにするのか、実際にセックスの動きに耐えられるように強度をどう保つかとか、読んでいると、まったく苦労が絶えない難問ばかりなのが分かる。それでもめげずに試作を重ねて、やっと光明を見出すところなど、まったくもって関心させれれる。何でもそうだが、すんなりと苦労もなく進む仕事なんてないのだと思い知らされる。
そんなラブドールを愛でる愛好家の話も興味本位ではなく、きちんと聞き、日頃表に出ることのない日常生活やちょっぴり笑えるエピソードなども取り上げられているところにも好感が持てる。
いったいどんな人が購入しているのか?
人形とセックスはやっぱりするのか?
手入れとかはどうするのか?
そんな素人の疑問も、読めばなるほど・・・と、氷解する。
写真もあるので、通勤電車で読むのには抵抗あるが、ちょっと時間の空いた時にでも、ペラペラとページをめくると面白く読める。ちなみにワタクシは、おおかたトイレと風呂で読みました(笑)
『AMON デビルマン黙示録』 [書評]
これも先に紹介したもの。
我々中年世代にとって『デビルマン』は特別な存在だ。
同格には当然『あしたのジョー』、『巨人の星』、『タイガーマスク』が続く。
ちなみに永井豪の作品では『バイオレンスジャック』のファン。『執天童子』とかも好き。
説明するまでもないとは思うが、タイトルの "AMON" とは、不動明に乗り移るデーモンの名前。
ちなみにこの作品は、オリジナルアニメのマンガ化らしい。なので、これまで散々語られてきた『デビルマン』のストーリーと解釈をは一線を画すものとなっていて、原作のテイストは守りつつ、AMON の過去やシレーヌとの関係という、これまでにない部分にスポットを当てているのが興味深い。
デビルマンではない "AMON" という、デーモン族の中でも勇者と呼ばれるほどの存在もまた異端であり、シレーヌもまた白き身体を持つ者として、シレーヌ族の異端であった。そんな異端と異端が出会った時、物語は急速に回転し始める。
AMAZON の書評にもあった通り、残念ながらAMON の物語は4巻まで。以降、「デビルマン」としての完成された物語の中に収められてしまうのはいささかもったいない気がする。
その代わり、堕天使サタン=飛鳥了の、不動明への愛情物語という要素が表に出てくるので、その点は面白かった。オリジナルよりもさらに明確になった愛憎物語は、オリジナルコミックの最後のひとコマの種明かしでもあるのだろう。
我々中年世代にとって『デビルマン』は特別な存在だ。
同格には当然『あしたのジョー』、『巨人の星』、『タイガーマスク』が続く。
ちなみに永井豪の作品では『バイオレンスジャック』のファン。『執天童子』とかも好き。
説明するまでもないとは思うが、タイトルの "AMON" とは、不動明に乗り移るデーモンの名前。
ちなみにこの作品は、オリジナルアニメのマンガ化らしい。なので、これまで散々語られてきた『デビルマン』のストーリーと解釈をは一線を画すものとなっていて、原作のテイストは守りつつ、AMON の過去やシレーヌとの関係という、これまでにない部分にスポットを当てているのが興味深い。
デビルマンではない "AMON" という、デーモン族の中でも勇者と呼ばれるほどの存在もまた異端であり、シレーヌもまた白き身体を持つ者として、シレーヌ族の異端であった。そんな異端と異端が出会った時、物語は急速に回転し始める。
AMAZON の書評にもあった通り、残念ながらAMON の物語は4巻まで。以降、「デビルマン」としての完成された物語の中に収められてしまうのはいささかもったいない気がする。
その代わり、堕天使サタン=飛鳥了の、不動明への愛情物語という要素が表に出てくるので、その点は面白かった。オリジナルよりもさらに明確になった愛憎物語は、オリジナルコミックの最後のひとコマの種明かしでもあるのだろう。
『秋葉原耳かき小町殺人事件』(吉村達也) [書評]

『秋葉原耳かき小町殺人事件/吉村達也』(ワニブックス【PLUS】新書)
タイトルにもなった『秋葉原耳かき小町殺人事件』とは、まだ記憶にも新しい、実際に起きた殺人事件を題材にしたノンフィクションである。
作者の吉村達也氏は、推理小説家として、かなりの数の作品を発表している現役バリバリの方で、ここでは職業として常日頃から殺人事件を編み出す作家としtえの特質を生かしつつ、事件の真相に迫ろうとしている。
事件のあらましは以下の通り。
浴衣姿の女性の膝枕で耳かきをしてもらえるのを売りとした新風俗店が登場し、一躍マスコミの話題となった。
2008年、19歳の少女がそんな店の秋葉原店に勤務するようになる。源氏名を「まりな」という。店は風俗店とはいいながら、エロ度は限りなく低い。しかし、浴衣姿の女性の膝枕で耳かきをしてもらうという行為が癒しを欲する現代人に受けたようで、けっこう繁盛した。
まりなをひいきにする常連客の一人に「よしかわサン」と名乗る男がいる。四十代前半だ。彼は土、日には必ずというほど予約を入れ、数時間をまりなと一緒に過ごす。やがて数時間が、5~6時間と伸び、また、金曜にも予約を入れるなど、次第に彼女を独占するようになる。
まりなも一風変わったこの男性に対していぶかしく思わなかったわけではなかったものの、必ず指名してくれて、長時間店で過ごしてくれるので、金銭的にも逃したくなかったようだ。
そんな状態が一年以上続き、さらにプレゼントや差し入れも彼女に手渡すようになったよしかわサンは、自分は彼女に気に入られていると思い込み、より親密になろうとする・・・。
と、細かいニュアンスはちょっと違うのだけれど、まあ、こんな感じで、簡潔に文字にすると何だかありふれた事件でしかないように思われることだろう。
事件は結局のところ、ストーカーが起こした殺人事件として処理される。
しかし、作者は、新しく誕生した裁判員制度裁判の審理を通して、この残酷極まりない事件が、なぜ「死刑」ではなく「無期懲役」と判断されたのか? に焦点を当ててゆく。
と、同時に、「まりな」の何がよしかわサンを惹きつけ、よしかわサンが惹きつけられたのかも解き明かす。それには「まりな」の無防備過ぎる無垢さがあり、それが店のホームページにUPされるブログ、特に、お客として訪れた人が書き込んだメッセージへの返答という今日的なシステムに支えられてのことでもあったのを見逃すわけにはゆかない。
書き連ねられた文字がすべてを表すわけもないのに、それを目の当たりにしてのめり込んでしまうという行為は、一度は誰にでも経験のあることだろう。インターネットの出始めの頃、掲示板に書かれた一言に過剰に賛同したり、反発したり、書き込んだりとか。そこには真実もある替わりに嘘もかなりの数存在する。そういうものだと割り切れれば、人は安易に何かにハマったりしないのだが、もともとが人と対峙するのが苦手な人にとっては、なかなか難しい。
そんな店の指名NO.1のまりなと、常連客のよしかわサンの出会いから事件、そして結審までを追いながら、事件を回避する分疑点がどこにあったのか、避けられるはずだったはずなのに、、、と、作者は心を砕く。
そして、よしかわサンにとって、耳かき小町の「まりな」という女性が何だったのかの<真相>を、推理作家らしい視点で導き出した最終章は読み応えがあると同時に、哀しくもある真実として、ずいぶんと重い。
ps.殺人事件の舞台となった耳かき店は、現在も都内で営業を続けている。
店のホームページには、浴衣姿の小町たちの素顔と個人別のブログが華やかに彩られている。
『訴訟』(カフカ) [書評]

『訴訟/カフカ』(光文社古典新訳文庫)
『変身』だけは読んだ人もいるでしょう。
ある朝、目が覚めたら一匹の毒虫になっていた、、、
というフレーズ(うろ覚えですいません)は、カフカの作風を凝縮したような一文だ。
不条理=カフカの代名詞の如く、『変身』しかり、『城』、そしてこの『訴訟』も、状況設定からして尋常ではない。
『訴訟』は、過去、『審判』のタイトルで出版されていたのを、海外に習い、新たに変更したもので、光文社古典新訳文庫の一冊として出版するにあたり、刷新された。
物語は、銀行員のヨーゼフ・Kが、ある朝、突如として逮捕されるシーンから始まる。
しかし、逮捕はされたものの、身柄の拘束はなく、普通に仕事に出掛けることはOK。そもそも逮捕の理由も説明されずじまいなのだ。
逮捕理由も分らぬまま、呼び出されて審議されるものの、やっぱり逮捕理由は明かされず。裁判所らしき建物にいる女は言い寄ってくるし、建物の空気も淀んでいて、気分が悪い。
叔父を頼って弁護士と会えば、くだくだと弁護の心得を並べるだけで、一向に具体的な解決策を示してくれず、じゃあ、と、関係者と知り合いだという法廷画家を紹介してもらい、家に出向けば、これまた、ああだ、こうだと、曖昧な話しかしない。
と、万事このような感じで、ストーリーはまるきり終息せず。ただ、バカバカしいやり取りが永遠と続くこととなる。
後半、「大聖堂で」という章の中で交わされるKと聖職者の会話こそは、この狂った物語の肝となるのだが、
「だから、なんでお前なんかに用があるのか。裁判所はお前になにも要求しない。お前が来れば迎えてやるが、お前が帰るなら、去らせるまでだ」
と、最後に告げられた台詞に、謎は謎のまま、放置され、しかも、廻り続ける円環の如く、エンディングへは辿りつかない。
それでも、次の「終わり」と名付けられた章では、唐突にエンディングがやってくる。どうなるのかはここでは記さない。あまりの唐突さに愕然とさせられるのだが、この作品自体が未完の作品であることから、その後もカフカは物語を続けようと考えていた節がうかがえる。ならばこのエンディングはヨーゼフ・Kの観た一瞬の悪夢であったのかもしれない。しかし、仮に悪夢であったとしても、醒めてみれば、また、これまで通りの悪夢がなだらかに続いているだけだ。
カフカはユダヤ人だ。はるか昔から、ユダヤ人は迫害され続けた歴史を持つ。近代でも、ヒットラーによるユダヤ人迫害は最も忌まわしい記憶として我々の記憶に強く焼き付けられている。迫害されたユダヤ人にとっては、なぜ自分たちが迫害されなければならないのか、理解出来ないだろう。それは旧約聖書に登場するモーゼの頃の話だと言われても、それが現在の自分たちに何の関係があるのか? そう問いかけたくなるに違いない。
それこそ理不尽の最たるものだからだ。カフカが繰り返し描く、意味のない悪意の世界は、それゆえ、ユダヤ人の日常を形を変えて反映したものと考えられる。これが日常だとしたら、どう生きたらいいというのか?
なお、この作品は未完であり、書き残されていた(採用された)のとは別の断片を集めたものが、巻末のいくつかの章にまとめられている。
『薔薇の名前』(ウンベルト・エーコ) [書評]


『薔薇の名前/ウンベルト・エーコ』(東京創元社)
ショーン・コネリー主演で映画化されたものの原作本。
作者は記号論で著名なウンベルト・エーコ。
映画公開当時、文芸サイズの上下巻各2000円にもかかわらず、ほとんどの書店では平積みになっていた記憶がある。
あれから30数年、なぜか未だ文庫化されず。しかし古本としてはずいぶんと安く手に入るのが以外だが、考えるに、売れた数に対して破読した人の数が極端に少ないのがその原因ではないだろうか? それくらい読み通すには覚悟が必要なのだ。
記号論と言われても何のことやらさっぱり、、、。
これがほとんどの人の反応だろう。かく言うワタクシも、知りません。ただ、記号(あるものに割り当てられた呼称であり象徴)の意味することとは? 逆に、意味と記号の結びつきは? とかに想いを馳せると、スイスの言語学者ソシュールや、オーストリアの現象学者フッサールをのこと想い出すのも、あながち外れてはいないと思われる。実際の物とその名称の関係は・・・。
なんてのは、長くなるのでこの歳割愛。そんなことを考えなくても映画はエンターテイメントとして十分に楽しめる作品となっていた。しかし、こと原作に限定すると、ちょっと一筋縄ではいかないようなのだ。
★ ★ ★ ★
表の物語が⇒フランチェスコ会修道士のウイリアムが弟子を引き連れ、歴史的にも重要な修道院で起きた殺人事件の謎を追うのに対し、
裏の物語は⇒イタリア宗教史の暗部
となっている。
表と裏と勝手に名付けたものの、本来なら裏こそ表で、表は裏なのだ。殺人事件こそが付け足しで、イタリア宗教史の方が本流と言い切ってさしつかいないだろう。それくらい比重に違いがある。実際に書かれている長さを比べれば一目瞭然、イタリア宗教史の方が段違いに多い。それからすると、イタリア宗教史を読ませるために、分かり易い殺人事件を挿入したと解釈してさしつかいないだろう。
【修道院殺人事件】
聖書の中でも最も有名な「黙示録」を題材に、修道士が次々に殺害されてゆく。「黙示録」のキーワードは<7>で、7人の天使の鳴らすラッパに合わせて訪れる惨劇を模した形で殺人が行われる。修道院の中では男色や売春もどきの行為が横行していたり、イタリア中探しても類を見ない複雑怪奇な建築方法を持った図書館と、幻の書物が重要な役割を担う。
ウイリアムと弟子のアドソはさながらホームズとワトソンの如く、事件の解決に当たる。登場人物表では、パスカヴィルのウイリアムとあるように、まさにホームズ、なのだ。
【イタリア宗教史の暗部】
イタリアといえば、古代ローマ帝国がキリスト教を国教として以来、キリスト教の本拠地的な立場にある国だ。しかし、本拠地とはいいながらも、キリストの教えをどう解釈するかについては、多様な考え方があり、それは××派という形で分離、独立している。『薔薇の名前』はそんなイタリア宗教界の暗部を描いたものとして、貴重な資料と考えられる稀有な作品だ。
殺人事件の舞台となる修道院、そこで繰り広げられる権力争い、ドロドロとした人間模様、それらはそのままイタリアキリスト教史へと置き換えられる。その模様を目の当たりにするのが、フランチェスコ派の司教のウイリアムだ。フランチェスコ派は聖フランチェスコと呼ばれた<清貧>を良徳と考える僧侶の教えを守る一派であり、いわば権力闘争の舞台においては “よそ者” となる。なので、第三者的な視点でもって、身内の暗部を露にすることとなる。
そしてここでは、《正統VS異端》《所有VS清貧》《魔女裁判における裁く者VS裁かれる者》等、背反する2つの事柄を対立させることによって、隠された宗教の裏側を焙り出す。
日本人か考える宗教感と、ヨーロッパのそれとでは、実際のところかなりの隔たりがあるのが、この作品を読めば理解出来るに違いない。それゆえ理解するにはある程度の予備知識を必要とするのもまた事実。
ただ、そのハードルを越えてしまえば、確かに世界的ベストセラーになるのもうなずける(特にヨーロッパでは)はずだ。
『存在の耐えられない軽さ』(ミラン・クンデラ) [書評]

『存在の耐えられない軽さ/ミラン・クンデラ』(集英社文庫)
ずばり、『存在の耐えられない軽さ』とはどのような意味なのか?
この奇妙だが目にした人を引きつけづにはおかないタイトルのおかげで、何人の人が手に取り購入したことか。特に女性には絶大なものがあるようだ。
知り合いの奥さんだか誰かが、この作品が生涯のNO.1! と言い切っていたのを聞いて、そうなの~?とか、野暮な男としては思ったりもしたけれど。
で、なんだ、その、『存在の耐えられない軽さ』の意味だっけ?
いわゆる、他人にとって、自分が ”ONLY ONE” ではないという屈辱、NO.1ではなくNO.2でしかない程度の存在感には、まったくもって耐えられない、、、と。
これは登場人物の一人、サビナがフッと思ったこと(この通りではないけれど)。
サビナはトマーシュの愛人で、テレザは彼の本妻。物語はこの3人を軸に、それぞれの物語を語りながら、密接に絡み合う関係を描く。ではテレザは愛の勝利者としての栄光を手に入れたかといえば、それも微妙なところがあり、彼女は彼女で悩みは尽きないようである。
サビナの悩みも、テレザの悩みも、もとをたどれば優柔不断なトマーシュに原因があると、男の視点では単純に解釈してしまってお終いなのだが、どうも女性の感想はそんな単純ではないらしい。
作者のミラン・クンデラは作中で物語を進行する役割も兼ね、ところどころ出て来ては、自分の考えなりを語ってしまう趣向は珍しくはないかもしれないが、ここまで頻繁だとうざったい部分も感じつつ、それがこの作品を他と区別することに一役買っているのも事実。
ページを開いたのっけからニーチェの永劫回帰話だし・・・。
それに加え、作者はチェコの作家であり、物語の舞台となるチェコスロバキアは、ポーランドともども、ドイツ侵略の脅威をモロに被った国でもある関係上、本来はそこまできちんと押さえておくべきなのだが。
とにかく、その他大多数の絶賛派に反して、残念、ワタクシ、それほど傑作だとは思わなんだ、、、。
いかにも考え方がヨーロッパ人特有の生真面目さから逃れられていなくて、トライアングルを形作る関係性も、それぞれの役割がどこか類型的な感じがして、、、。う~ん、ごめん!
記憶の中の本を探す [書評]
先の着物の美女との飲みの時に、偶然話題になった、『昔読んだ本を探す話』の、こちらは実践編。
その経過を、思い込みを廃し、事実だけをここに記すことにする。
まさに<記録>である。
MISSHION:『記憶の中にある本を探すこと』
記憶:①読んだのは30年以上昔
②作者がロシアの作家でありこと
③短編であること
④「物語」小さい頃から、美人だねと母親や祖母に言われて育った少女は、ある日、容姿のことで男の子にからかわれる。
実は自分がそれほど美人ではなかったと、初めて自覚させられることによって、少女という時代の終わりを描いた作品
まず浮かんだのがロープシン
しかし、ロープシンは政治的な内容の『その馬を撃て』の作者であり、間違いの可能性大
次にガルシンの名が浮かぶ それも著書名『赤い花』が瞬時に連想される
ウィキで調べると、短編作家ではあるものの、『赤い花』の内容も政治的なものであり、他の短編もどうやら該当しなさそう
検索⇒ロシア、短編小説、少女、などを入力
「美人ごっこ」というタイトルが浮かぶ
その作品を含む著書名が『初恋物語』であることが判明 作者はユーリー・Y・ヤーコブレフ。
「美人ごっこ」の内容を紹介する文がないかさらに検索するも、該当なし
↓
「美人ごっこ」を本命と決め、さらに捜索
☆ ☆ ☆
【2010.12.16】
千代田区図書館のホームページで蔵書検索
該当なし
国会図書館のホームページで同様に検索
該当19件
しかし、関東圏では、茨城県立図書館、千葉県立中央図書館、千葉市中央図書館、川崎市立中原図書館のみ
千代田区図書館に連絡
該当図書館の本は取り寄せ可能かを問い合わせる
取り寄せ可能だが、送料負担が発生するとの回答を得る
東京都立図書館で検索してみるようアドバイスされる
東京都立図書館のホームページを検索
都立多摩図書館に在庫あり
*念のため、AMAZONでも検索
同じ内容の作品が出品者から出されているのを確認するも、もともとが図書館話から派生したことなので、この時点では購入せず
【2010.12.17】
都立多摩図書館のホームページを検索
所蔵一覧に掲載されているのを確認
閲覧可能なれど貸出不可とある
電話にて現物があるかを問い合わせる
確認してもらい、1時間後に再度連絡
現物ありの返答
翌日、時間が取れればうかがう旨を伝える
【2010.12.18】
立川駅より徒歩で都立多摩図書館へ
窓口に昨日の話をして、取り置きの本をもらう
タイトル:『美人ごっこ』 作者:ユーリー・Y・ヤーコブレフ
その本は予想していたものとは違い、小学生向けのジュニア版(B3?)だった
さっそく内容を確認
確かに昔に読んだ記憶がある(ただし、このサイズではなく)
作品のコピー(半分までとの規制あり)を取り、返却
【2010.12.19】
再度AMAZONを確認し、購入
後日、送られてきた本『初恋物語』を手に取り、記憶の中にある旺文社文庫版(1974年刊行)であった
そこに収録されている「美人ごっこ」を読み、これこそが30年以上昔に読んだ現物であるのが判明
BINGO!!!

これが今回の記事の主人公。お前、久しぶりだなあ~。
その経過を、思い込みを廃し、事実だけをここに記すことにする。
まさに<記録>である。
MISSHION:『記憶の中にある本を探すこと』
記憶:①読んだのは30年以上昔
②作者がロシアの作家でありこと
③短編であること
④「物語」小さい頃から、美人だねと母親や祖母に言われて育った少女は、ある日、容姿のことで男の子にからかわれる。
実は自分がそれほど美人ではなかったと、初めて自覚させられることによって、少女という時代の終わりを描いた作品
まず浮かんだのがロープシン
しかし、ロープシンは政治的な内容の『その馬を撃て』の作者であり、間違いの可能性大
次にガルシンの名が浮かぶ それも著書名『赤い花』が瞬時に連想される
ウィキで調べると、短編作家ではあるものの、『赤い花』の内容も政治的なものであり、他の短編もどうやら該当しなさそう
検索⇒ロシア、短編小説、少女、などを入力
「美人ごっこ」というタイトルが浮かぶ
その作品を含む著書名が『初恋物語』であることが判明 作者はユーリー・Y・ヤーコブレフ。
「美人ごっこ」の内容を紹介する文がないかさらに検索するも、該当なし
↓
「美人ごっこ」を本命と決め、さらに捜索
☆ ☆ ☆
【2010.12.16】
千代田区図書館のホームページで蔵書検索
該当なし
国会図書館のホームページで同様に検索
該当19件
しかし、関東圏では、茨城県立図書館、千葉県立中央図書館、千葉市中央図書館、川崎市立中原図書館のみ
千代田区図書館に連絡
該当図書館の本は取り寄せ可能かを問い合わせる
取り寄せ可能だが、送料負担が発生するとの回答を得る
東京都立図書館で検索してみるようアドバイスされる
東京都立図書館のホームページを検索
都立多摩図書館に在庫あり
*念のため、AMAZONでも検索
同じ内容の作品が出品者から出されているのを確認するも、もともとが図書館話から派生したことなので、この時点では購入せず
【2010.12.17】
都立多摩図書館のホームページを検索
所蔵一覧に掲載されているのを確認
閲覧可能なれど貸出不可とある
電話にて現物があるかを問い合わせる
確認してもらい、1時間後に再度連絡
現物ありの返答
翌日、時間が取れればうかがう旨を伝える
【2010.12.18】
立川駅より徒歩で都立多摩図書館へ
窓口に昨日の話をして、取り置きの本をもらう
タイトル:『美人ごっこ』 作者:ユーリー・Y・ヤーコブレフ
その本は予想していたものとは違い、小学生向けのジュニア版(B3?)だった
さっそく内容を確認
確かに昔に読んだ記憶がある(ただし、このサイズではなく)
作品のコピー(半分までとの規制あり)を取り、返却
【2010.12.19】
再度AMAZONを確認し、購入
後日、送られてきた本『初恋物語』を手に取り、記憶の中にある旺文社文庫版(1974年刊行)であった
そこに収録されている「美人ごっこ」を読み、これこそが30年以上昔に読んだ現物であるのが判明
BINGO!!!

これが今回の記事の主人公。お前、久しぶりだなあ~。
『大穴』(ディック・フランシス) [書評]
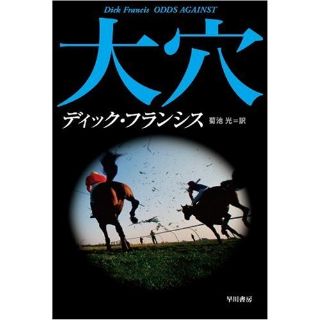
『大穴(Odds Against)/ディック・フランシス』早川文庫
久々のハードボイルド・ミステリー。それもフランシスとくれば、内容は保証されたも同然。
米国産の、砂埃(すなぼこり)と鉛の玉が飛び交うそれではなくて、ちょっとばかり湿り気を帯びた芳しい英国産ミステリーをとくとご堪能あれ。
STORY:かつて名騎手として輝かしい戦歴を収めたシッド・ハレーは、落馬事故が原因で騎手を引退する。左手を馬に踏まれたのが致命傷となったのだ。そのおかげで左手は使い物にならなくなってしまった。現在はラドナー探偵社に勤務しているものの、ふ抜けた死人同然だった。
そんな時、かつて疾走したことがある競馬場が何者かの手によってレースの妨害にあっている疑惑が浮上する。それを受けて株価も暴落。だが、そんな株券を買い漁る一人の男の存在が・・・。
ディック・フランシスはかなりの作品を残し、今年、惜しまれながらも他界した。
彼のの作品はどれもイギリスの競馬会を舞台にしたものばかり。なぜなら彼自身が競馬の騎手だったからだ。なので自分の庭を描いたような作品は、どれも細部まで詳細に書き込まれ、読む者をうならせる。もちろん競馬の知識がなくても十分楽しめる。
そんな作品群にあって、中でも最も人気のあるのが、シッド・ハレーが登場するシリーズで、『大穴』『利腕』『敵手』『再起』の4作品が書かれた。なぜかフランシスは作品の割にシリーズ物が少なく、ほとんどが単発物となっている。シッドを主人公にした作品をもっと読みたいと思っている人が世界中にどれくらいいたか。スペンサー・シリーズのようにタラタラ無意味に(失礼!)続けるのも如何なものか、なのだが、4作品というのは少な過ぎる。
シッドが身を置くのがラドナー探偵社。探偵社とは言っても、競馬にかかわる保険関係の調査が主な業務らしいので、米国製ハードボイルドのように、孤独な一人捜査とはいささか異なる。仲間と組んでの調査なのだ。それでも探偵社なんてのは、やはりどこか世間からはじかれたような人種が集まるようで、社長や同僚も、社会のルール以上に自分のルールに趣きを置く傾向にある。
さらにシッドは奥さんと別居中だし、離婚手続きも勝手に進められている。彼の方は未練タラタラで、事あるごとに彼女を想い出しては、ウジウジ悩んだりしている。
シリーズ第一作目のこの作品でシッドは、騎手としての自分に別れを告げ、大切な競馬場を救うため、危険を伴なう事件の調査を通して、新しい自分の居場所を見つけることになる。
フランシスの筆は必要以上に感傷的になることを避つつ、米国にはない英国の香り漂う物語を創造し、シッドという魅力的なキャラクターを世に送り出すことに成功している。
『チャイルド44(上下巻)』 [書評]

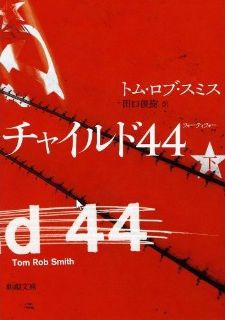
『チャイルド44 / トム・ロブ・スミス』
『妻は、くの一』を読む前に読んでいたのが、実はこの『チャイルド44』。
著者はトム・ロブ・スミス。これがデビュー作だ。
物語はスターリン体制下のソ連。年代にすると1950年代。
国家保安省の捜査官であるレオは、社会主義国家ソ連を担う一員となって社会のために尽くしていた。
そんな彼が遭遇したのが、部下の子どもが何者かに虐殺された事件だった。
しかし、理想国家ソ連に凶悪犯罪などあってはならないというイデオロギーのもと、虐殺を事故死として処理してしまう。
それからしばらくした後、同じく子どもの虐殺死体が発見された。口に泥のようなものが詰め込まれ、おまけに胃が切り取られ、足首には紐が結ばれていた・・・。
実在の大量殺人鬼をモデルとして描かれた『チャイルド44』。なので当然、物語の本筋は子ども殺しではあるものの、犯人は最初からだいたい予想がつく。殺す理由は分からなかったけれど。
それよりも、幼児虐殺事件を題材にして、作者が本当に描きたかったのは、人民のための理想国家であるソ連の内情。
理想国家とは名ばかりの、同じ職場の仲間でさえもまったく信用出来ず、いつ弱みを見つけ、上層部に密告されるのか分からず、いつもビクビクとしていなければならないのだ。
主人公のレオも、行き過ぎた捜査を強引に推し進める部下のワシーリイを戒めたことが彼の恨みを買い、それが原因で左遷させられる。
それと同じくして妻のライーサを狙って別の国家保安省の医師が、彼女に自分の愛人になることを強要。それが叶わぬと、西洋社会に通じた国家転覆を狙い危険分子として告発する。告発に証拠はいらない。告発されたという事実さえあればそれでいいのだ。
これまで信じていた社会、妻の愛情等がガラガラと崩れ去った後、レオを現実につなぎ止めるのは、過去、自分がろくに事実を調査もせず事故死にした部下の子どもの殺人事件であった。あの時の犯人がその後の連続殺人犯として生きているのをほおってはおけない。ただその一点のみに突き動かされて犯人を追う。
社会主義が敗北に終わったのは、ほぼ歴史的事実になろうとしている昨今、ベールに包まれたあの時代の雰囲気を生々しく伝えるミステリーとして、この作品の価値は高い。
『妻は、くの一』 [書評]
まじめな本を読んだ後、もしくは暑過ぎてまともな本など読みたくもない!
・・・と、そんな考えは誰でも抱くもの。
ちょうど "疲れた時の西村京太郎" のように。
本屋をブラブラするのが好きだ。
一時間くらいなら楽に時間をつぶせるし、新刊本を陳列してある平台を眺めるのも楽しい。
ここ数年歴女ブーム(我が家の嫁さんは元祖歴女です!)と時を同じくして、出版界も時代小説ブームのようで、あるは、あるは、ところ狭しとその手の小説が並べられております。
で、タイトルに惹かれて手に取ったのが、『妻は、くの一』。
作者の風野真知雄という方は初耳。でも、くの一シリーズ、現在まで7巻を数えるほどの人気を得ている大ヒットなのだった。
主人公は彦馬は取り立てて美男でもなく、藩の中では出世頭でもなく、おまけに剣の腕は三流。望遠鏡で星を眺めるのが大好きな、かなりの変わり者。
そんな彦馬に縁談が持ち上がる。相手は細面のかなりの美人。それがどうゆうわけか彦馬の妻になるのだが、実は彼女はくの一。任務が終わると彦馬の前からプッツリと消えてしまう。
なぜ妻が突然いなくなってしまったのか理解出来ない彦馬は、彼女を探しに早々と藩を隠居し、江戸へ。
一方、彦馬の不器用だが嘘のない性格に惚れてしまったくの一の織江も、次の任務のさなか、彦馬に会おうとするのだが・・・。
文の運びもスムーズで、読んでいても突っかかるところがなく、スラスラと読み進むことが出来るのが嬉しい。その点では暑苦しい今の季節には持ってこいの一冊だろう。
ただ、逆の見方をすれば、薄味で物足りないと感じる読者もいうだろうことは容易に察しがつく。
ボクは残念ながら後者。避暑地にでも持って行くにはベストとは思うものの、スラスラ読める分、やっぱりコクはない。アメリカンコーヒーも時にはいいが、いつも飲もうとは思わないのと一緒。それに加え、一冊で物語は何も完結しない。まさに to be continue・・・。
通勤読書で2~3日あれば読み終わる。
後、入院中の人にもお勧め。
『潮騒の少年』(ジョン・フォックス) [書評]

『潮騒の少年/ジョン・フォックス著』(新潮文庫)
BOOK OFFで105円で売られてました。
安いので買ってみました。で、内容はというと・・・。
ニューヨークのハイスクールに通う16歳のビリーは、ごく普通の元気のいい高校生なのだが、ひとつ、他の子たちと違うところがあった。それは彼がゲイだということ。
水泳部に所属するビリーは、同じ部活仲間のエヴァンとケヴィンのお尻に見とれたり、他で目に入ったかわいい男の子を思い出しながらマスターヴェイションをしたりしてしまうのだが、そうではあっても、必要以上に自分がゲイであることを悩んだりはしない。もちろんまったく悩まないわけではないのだけれど、わりと自然にそれを受け入れているのだ。
もちろん、周りは彼がゲイだと知らないから、女の子とのダブルデートを計画したりする。ビリーも迫ってくる女の子とセックスをしてみたりもするのだが、やっぱりどこか違うと思ったりする。
そんなビリーはたまたま大統領候補マッカーシーの選挙運動をするアルを見て、ひと目で魅了されてしまう。挙句に運動員にならないかというアルの勧誘に、待ってました! とばかりに乗り、二人は急接近。
そんなアルとビリーの、期待と不安を抱きながらも、お互いの距離を徐々に縮めてゆく様は、男と女じゃない、男と男ではあっても、青春小説としてとてもよく描かれていて共感が持てる。性別は違えど、恋する心は世界共通というやつだ。
と、ベタボメしたものの、水泳大会で泳ぐビリーが、応援に駆けつけたアルが別の少年と話しているのに嫉妬心を燃やす(それも目撃したのが泳いでいる最中とは!)あたりは、あまりに嫉妬深くてついてゆけない。それと具体的なセックス描写も(というほどではないにしても)ちょっと・・・。
それでもキワモノとは一線を画す青春小説の傑作に仕上がっていると思う。
まずこの作者、文章がバツグンに上手い。それは同時に翻訳をした越川芳明氏にも言えて、文字の密度もかなり濃いにもかかわらず、一度読み始めたらスイスイと読み進めてしまえる文章のリズム感は、他の作品ではあまりお目にかかれない代物だ。
さて、めでたく結ばれたビルとアルは、その後どうなったのか?
続きはぜひご自分で読んでみて下さいな。
『黒河を超えて』(コナン・シリーズ) [書評]

『黒河を超えて/ロバート・E・ハワード著<新装版コナン全集>』(創元推理文庫)
SF同様、ファンタジー小説もまず読まないんですけど、唯一、マーセデス・ラッキー作の<女剣士と女魔法使い>を主人公にしたシリーズは面白く読めました。ちょうど『ロード・オブ・ザ・リング』の一作目が公開された頃だったと記憶しています。
それに次いで、、、と言ったって、もう何年も読んでいないので、次いでではないのですが、ファンタジー小説の源流とも呼ばれる<コナン・シリーズ>を読んでみました。文庫本の装丁にあるように、どうやら新しく翻訳し直されたもののようです。
紹介文には<ファンタジー小説の源>と書かれている通り、ここに収録されているのは、1934年に書かれ、翌年に雑誌『ウイアードテイルズ』に発表された3作品で、信じられないことに、すでに75年も昔の作品なのということになります。
舞台設定は架空の古代世界。キンメリアと呼ばれる国に生まれたコナンが、世界をさ迷い経験した数々の冒険譚が物語の中心となっています。
どの作品も長編ではなく中篇として描かれているので、コナンの成長物語としてよりも、忘れた頃にふいに届けられる遠く離れた異国の友人からの便りのように、全貌というよりは、ある限定された物語の一端を切り取って見せられたかのような気にさせられます。
以前、アーノルド・シュワルツネガーにより製作された映画を覚えていらっしゃる方も多いでしょう。当時、ボディビルダーとしてその世界に名を轟かせていた彼が、持ち前のムキムキ度100%で活躍する冒険ファンタジーとして、かなり話題になっていました。映画はそれほどヒットしなかった(少なくても日本では)ように記憶していますが、改めて原作を読んでみると、それではシュワルツネガー以外に誰がスクリーン上でコナンを演じられたかは難しい問題に違いありません。というのも、原作のコナンは身体が大きく、野性味に溢れ、原始的なパワーみなぎる人間離れした傑物なのです。それでいて女好きで知性的なもう一つの正確も秘めています。確かにこんなキャラクターを想像上ではなく現実に活躍させるとしたら、かなり悩ましいことになるに違いありません。
それに加え、架空の世界を舞台にしたファンタジー小説ゆえ、登場する敵もまっとうな人間ばかりとは限らず、魔術師だったり、怪物だったりと多種多様。さすがに人間離れしたコナンではあっても、打ち負かすには並大抵ではありません。
物語には必ずといってよいほど、敵、味方の区別なく、美女(それもアマゾネス級の)が登場するのも楽しみの一つでしょう。気性の激しい女盗賊やら女海賊やら、強くて美人で、それでいてフェロモン放出し放題なヒロインたちは、男性読者にとっては必要不可欠。そもそも雑誌『ウイアードテイルズ』の読者の99%は男性でしょうから(笑)
『世界の神々がよくわかる本』 [書評]
『世界の神々がよくわかる本』(PHP文庫)
『タイタンの戦い』で触れた神話の世界を、せっかくだからもう少し知りたくなったので、娘の持っている『世界の神々がよくわかる本』を借りて読んでみた。以前から何気に本屋で平積みになっていたので、きっと隠れたベストセラーなのだろう。その証拠に、わずか半年の間に14版という驚異的な増刷を行っているのが、巻末に見て取れる。
★
内容は子ども向けに編集されているので、それほど難しくないし、それぞれの神々の説明にはイラストが描かれており、より具体的なイメージを読む人に与えてくれるのがありがたい。
以下、ギリシャ神話に登場する代表的な神々を、簡単にまとめてみたので、興味のある方はカップラーメンでもすすりながらボーッと眺めていただけたらよろしいかと。
【その世界観】
ギリシャとあるように、元を正せば古代ギリシャ文明が起源。紀元前9世紀頃にはすでにオリンポスの神々のことを敬う習慣があったそうだ。神話は「創生神話」「神々の神話」「英勇たちの神話」に分かれ、そこに描かれているのは、<天地創造~ティタン族の支配~オリンポス神がティタン族を滅ぼす~ゼウスと兄弟、それらの子の物語~人間の英雄たちとオリンポスの神々の物語~>となっている。
ゼウス:オリンポス12神の長。気象を操り、雷を武器とする。父親クロノスを戦(いくさ)で打ち破り新たな王となる。女好きであちこちの女に子どもを産ませる。
ポセイドン:ゼウスの兄。ゼウスが世界を3分割した際、海の王となる。12神のナンバー2。
ハデス:ゼウスの兄。こちらも3分割の際、冥界の王となる。しかしこれは本人の望んだものではない。なので映画ではゼウスに取って代わろうと画策する。
アポロン:太陽神であり、医学、数学、芸術を司るオリンポスの神々の中でも一番の美男子。
アルテミス:アポロンの双子の妹。別名「月の女神」。また、アポロン同様弓矢の名手で「狩猟の女神」とも言われている。
アテナ:「戦の女神」。アテナイの町の守護神の座を賭け、ポセイドンと争い、美しさをヘラ(ゼウスの姉であり妻)やアフロディーテ(別名ヴィーナス)と争う。
アフロディーテ:神々随一の美貌。別名「美と愛の女神」。浮気好き。夫以外に複数の愛人を持つ。ゼウスの祖父ウラノスの切り取られた男根が海に落ち、そこから溢れ出した泡から生まれたとされる。
アレス:「軍神」。ただし、その戦い方は乱暴で知性に欠ける。アフロディーテと不倫。
と、まあ、こんな感じで、いるわいるわ。
ピンからキリまでズラーッと取り揃えております。神様と言ったって決して品行方正ではありません。それどころか、あまりに人間らしい方々ばかり。 ・・・いや、待て。神様が我々に似ているんじゃなくて、我々が神様に似ているんだな、順番的には。
まだまだいるのですが、全部を網羅するにはこのブログでは足りません。なので、残りはぜひ自分で調べてみて下さい(無責任過ぎるぜ!)。
ボクも一度、ちゃんとギリシャ神話を読んでみたくなりました。いつになるかは分からねど。
『片目の猿』(道尾秀介) [書評]

『片目の猿/道尾秀介』(新潮文庫)
これまた驚愕のミステリーの系譜らしい。
作者の道尾氏は、先に書いた石持浅海同様、若手の注目株らしく、2007年の本格ミステリベスト10では、選考期間内に出た3作品すべてが10位以内にランクインするという快挙を成し遂げたことで、大注目された、、、と、巻末に書かれていた。
「驚愕の真相」なる言葉は、皮肉なことに、まったく逆の意味で驚かされることの多い(笑)言葉として、すでにボクの中では定着してしまっているのが、哀しいが、過去の経験上、驚かされた作品は片手で数えるほど。後は・・・。
さて、ダメもとで古本屋で手にしたこの『片目の猿』はどうだろう?
書店では氏の旧作『向日葵の咲かない夏』(未読)と並べて陳列されていたりもして、それほどひどくもないだろう、、、と思ったら・・・
これが、ひ、ひどい!!!
こんなくだらない小説、今まで読んだことがない!
どこがひどいって、すべてと言うしかない。
全部、ダメなのだ。
これは別に生理的に受けつけないというレベルではなくて、白痴指数200% 話になっていないのだ。
ハードボイルド小説の形式を取っているにもかかわらず、まったくハードボイルドになっていない。それどころかハードボイルドのパロディにさえなっていない。
「私立探偵」が「一人称」で「俺」という名称を使えばそれですべてが済まされるのか?
もし、これをハードボイルドと認めてしまったら、チャンドラーやディック・フランシス(黙祷!)に顔合わせが出来ない。
どうでもいい謎は、読者に何の正当な提示もされないまま、実はこうだった、と、勝手に決められてしまい、
「どうだ、分からなかっただろう!」
と、声高に叫ばれても、
「はあ~???」
と、首を傾げるばかりだ。
「それがどうした?」
と、作者にまんま突き返してやりたくなってくる。
この作品、新潮社のケータイ文庫として配信されたものを書籍化したらしく、ケータイ小説自体をまったく評価しないボクにとっては、逆に、ケータイ小説読者にはこの程度(程度もなにもないのだが)でも面白いと感じる人がいるとしたら、それもまた驚異だ。そんな人には、
「頼むから古典を一度読んでよ!」
心からそう願わずにはいられない。
正直言って、らくがき以下。
資源のムダ!!!
『セリヌンティウスの舟』(石持浅海) [書評]
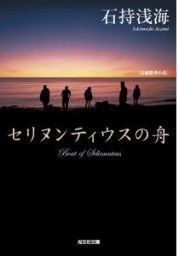
『セリヌンティウスの舟/石持浅海』(光文社文庫)
「またつまらないものを切ってしまった・・・」
は、ルパン三世の相棒である石川五右衛門の決め台詞として、あまりにも有名だが、最近の若手の小説を読んで、
「またつまらないものを読んでしまった・・・」
と、溜息をつくことも多くなった。読んでしまったならまだしも、読もうとしたのに読み進めなかった・・・というのも中にはあったりして、本好きもこれはこれでけっこうシンドイのよ! と、愚痴の一つもこぼしたくなる。
さて、石持浅海という作家は始めてである。
名前を眺めて、この人は海好きなのかな、と、考えていたら、案の定、『セリヌンティウスの舟』は、スキューバダイビングの話だった。
STORY:沖縄の海を潜るために偶然集まった6人は、荒波の中、遭難してしまう。お互いが手を繋ぎ、丸い人間の舟になることで、かろうじて事故を免れる。それ以来、6人は命を介した特別な仲間となった。
ある夜、6人が集まった家で、その中の一人である美月が青酸カリを飲んで自殺した。彼女の葬儀の帰り、残された5人は再び集まり、彼女の死を悼むことにするが、その死を論じれば論じるほど、単なる自殺ではない可能性が浮上してくるのだった。
青春推理物もたまにはいいか! と、購入した目論みは見事に外れ、最近の不調(自分の目利の)を裏づける結果になってしまった。
「走れメロス」を題材にしたところは良かった。信じる者と信じられる者の関係は推理小説には持ってこいだろう。文章も、ほとんど密室の中だけで行われる動きのない推理劇をよくこれだけ書けるなと感心する。筆力はかなりのものだろう。
では、何がダメなのか?
①まず、自殺する美月の肝心の動機が、まったくわからないこと!
普通、失恋したとか、不治の病だとか、借金したとか、何らかの具体的な事柄がなくてはならないはずなのに、それがスッポリと抜け落ちている。なので、死に対する興味も同情も湧いてこない。
②美月の自殺の協力者の存在と協力理由があまりにあいまい。
この曖昧さは美月の死の説明不測と同類。理由が理由になってない。
③登場人物の誰もが、血の通った人間として認識出来ない。
人間の死を問題にしているのに、登場人物の背景がほとんど描かれないので、生きた人間に思えない。
以上の点が読み終わった後の正直な感想だ。
まるで、単なる言葉上の<死>をキーワードに、作者がチェス盤上の駒を、操り人形よろしく、勝手にあちこち動かしているだけ。いわば、推理の為の推理なのだ。
それでも「このミステリーがすごい2006年度版」で前作(?)が第2位に選出されたらしいので、それからすれば世間では気鋭の新進作家の名に値するのだろう。でも、この作品を読む限り、本当にそうなのだろうか?
ここ2~3年はおもに国内外の古典を積極的に読み進めて思ったのは、さすがに時代を乗り越えて生き続ける古典は凄いというものだった。古典、恐るべしなのだ。
それでも若い力を時に感じたくなり、読んでみるのだが、結果はこの通り、芳しくない。
これならずーっと古典でも読んでた方がマシ、なんて思わせないで欲しいものだ。



